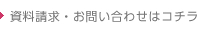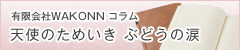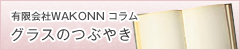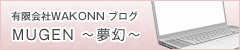2012年10月
第13回 伊野由布子さん
服部栄養専門学校で「ワインの基本とサービス」の講師を担当の伊野由布子さん。ご自宅ではワインとお料理のマリアージュの会を主催。ワインを中心とするお酒と、それに合うおもてなし料理を教えていらっしゃいます。また、雑誌やTVでレシピを紹介するなど幅広く活躍され、(社)ソムリエ協会の理事にも就任された伊野さんに、ワインとの出会いや料理研究家になられたエピソードや、ワインと料理に関するお話をお伺いしました。
「会いたい人がいると、どんなに遠くても会いに行き、美味しいものがあると聞けば、なんとしても食べたり飲んだりしてみたい。それに注ぐエネルギーは自分でも時々びっくりしますが、おかげで色々な美味しいものや素敵な人にめぐり合うことが多いです」と語る伊野さん。
 福岡出身の伊野さんが学生だった頃の話です。フランス料理とステーキで有名な博多の老舗レストラン「和田門」に勤めていたルームメイトが、その日お店で残ったワインを持ってよく遊びに来ていて、それを飲むのが楽しみになったのがワインとの出会いとのこと。
福岡出身の伊野さんが学生だった頃の話です。フランス料理とステーキで有名な博多の老舗レストラン「和田門」に勤めていたルームメイトが、その日お店で残ったワインを持ってよく遊びに来ていて、それを飲むのが楽しみになったのがワインとの出会いとのこと。
伊野さんのご実家では外で食事をしてワインを飲むという習慣がまったくなく、お父様もお酒は一滴も飲めなかったのですが、このルームメイトの持ってきてくれるワインがきっかけで、伊野さんは食事と共にワインをいただく楽しみを知りました。
初めて美味しいと思ったワインは、フランスはピュイイ・フュメの「バロン・ド・エル」。それまで飲んできた白ワインとは違う熟成感が伊野さんを惹きつけました。
幼い頃からお料理に興味を持っていた伊野さんは、お母様の婦人雑誌を開き、お料理や当時話題のシェフに関する内容をよくチェックしていたほど。図書館でも料理の本ばかり読むような子どもだったそうです。
当時は、フランスへ修行に出かけた若い日本のシェフたちが勉強を終えて帰国し、メディアを通じてフランス料理を日本中に紹介し始めた頃でした。
伊野さんは「東京に行ったら○○シェフの△△を食べよう」と心に思い続け、上京を機に早速レストラン回りをするようになったのです。
伊野さんがシェフの得意とするレシピを注文するので、レストランでは心したのでしょうね。
伊野さんの夢はお料理の先生になることでした。現在は服部栄養専門学校で講師を務めながら、ご自宅では一時間ぐらいで簡単にできる見栄えのよいおもてなし料理をワインに合わせて教えています。伊野さんのワインとお料理のマリアージュに惚れ込んで訪れる生徒さんは跡を絶ちません。
しかし、伊野さんがお料理の先生になるまでには色々な道のりがありました。
 東京へ出てきて料理の先生になりたいと思っていた頃、知人が服部栄養専門学校の服部校長を紹介してくれました。
東京へ出てきて料理の先生になりたいと思っていた頃、知人が服部栄養専門学校の服部校長を紹介してくれました。
服部校長に「お料理の先生になりたい」と話すと、「料理の先生はいっぱいいるけど、今からは料理プラスアルファ、なにか出来ないとだめだよ」と厳しい一言。「じゃあワインとお料理ではだめかしら?」と、とっさに答えた一言に、服部校長は「よいと思いますよ」とうれしい返事をくださったのです。
「レストランのワインリストもわからないのだから、これはよい機会だわ」と、伊野さんは東京のワイン学校として開校したばかりの「アカデミー・デュ・ヴァン」でワインの勉強を始めることになりました。当時のアカデミー・デュ・ヴァンの生徒は、ソムリエや料理専門職の方ばかりでした。
専門知識がない分、先入観の少ない伊野さんは素直に教えられたことを学び、習った通りにブラインドテースティングをするので、知識のあるクラスメイトより成績が良く、それがうれしくてまた勉強に励むのでした。
現在、自分が教えている服部栄養専門学校の生徒さんにも同じことを感じるそうで、知識がまったくない学生さんは、ワインの勉強を始めて半年ぐらいたつと、ブラインドテースティングがよく当たるようになるのだとか。でも2年ぐらい勉強を続けると、情報量が増え、当たらなくなることが多いそうです。
ワインの勉強をした後、フランスにお料理の勉強に出かけました。料理やパン、ファッションなど、国が奨励する分野を教える学校「パリ市商工会議所フェランディ校」で勉強を始めます。
料理学校は調理に使う道具や素材が本格的で、羊が一頭、牛が半身。それをさばき、料理をします。伊野さんは驚きながらも勉強に励みました。日本で学んだワインの知識が役立ち、フェランディ校の授業でも、ワインについては同じクラスの人より知識があったのです。
フランスで料理の勉強を終えて帰国した伊野さんは、再び服部栄養専門学校の服部校長を訪ねます。しかし服部栄養専門学校の先生になるまでにはまだ遠い道のりがありました。
帰国直後、友人のレストランから「うちのお店で働かないか」という誘いもありましたが、「お料理の先生になりたい」という夢を強く持っていた伊野さんは、レストランで働くのは自分の進む道とは違うと、思い迷っていました。そんな時、フランスへ勉強に行く前に受けることができなかったワインのクラスを受けようと訪れたアカデミー・デュ・ヴァンで、「伊野さん、アカデミー・デュ・ヴァンの事務をしてみませんか?ソムリエ試験に受かれば講師をやってもいいですよ」という機会にめぐり合ったのです。
1991年のことでした。「“先生”だったらやってみよう!」と思った伊野さんは一年間学校の事務職を勤め、試験に受かった後、アカデミー・デュ・ヴァンの講師になりました。
そのワインの講師は色々な事情で一年ほどで辞めることになり、「これからどうしようかしら」と思っていたところ、服部校長から「うちの学校で教えてみてはどうですか。ワインの先生はいないし、ちょうどいいよ」と、うれしいオファーがありました。
服部栄養専門学校でワインと料理の講師をすることになった時、今度はアカデミー・デュ・ヴァンから「諸事情で学校から先生方が引き抜かれてしまい、講師がいなくて困っているので、伊野さんに再びワインの講師をしてほしい」というオファーが来ました。
服部栄養専門学校ですでに講師をしているので、いったんはお断りをした伊野さんですが、服部校長からの意外な一言が彼女の進路を決めることになります。
「伊野くん、“学校”と言うのは存続させることに意義があるのです。どんなときも学校を存続させることを選択しなくてはいけません。君が行くことでアカデミー・デュ・ヴァンという学校が存続するなら、行ってあげるべきではないだろうか」
服部校長の“学校”に対する考えに感銘を受けた伊野さんは、それから両方の学校でワインを教えることになります。
アカデミー・デュ・ヴァンで事務局をしたり、ワインの講師をしたり、服部栄養専門学校でワインと料理の講師をしたりと、両立の日々は大変でした。しかし、服部栄養専門学校で18歳の学生に対する授業と、アカデミー・デュ・ヴァンに通う大人の生徒に対する授業の両方をこなした経験は、伊野さんに色々な年齢層の生徒に講義をする力をつけることになります。今では、講演の依頼が来ても、どのような聴衆に対してでも話ができるのは、その頃の経験のおかげだという伊野さん。アカデミー・デュ・ヴァンの講師陣が増え、無事に役目を終えた伊野さんですが、服部栄養専門学校の講師以外にも活躍の場がどんどん増えていきました。
ワインと料理
料理を作るのが好きで、友人知人を招いてお料理を作ってお食事をする機会が多い伊野さんのお気に入りのワインはピノ・ノワールだそうです。
「お料理教室では毎回料理に合わせたお勧めのワインを紹介します。
ワインを選ぶ際は、その年に訪問した国の影響があります。昨年はスペインを訪れたので、スペインの“チャコリー”を紹介しました」
チャコリーとは、バスク地方で産する白ワインで、独特の軽い酸味の利いた微発泡性の、4月~7月の間の季節限定のワインです。
注ぎ方も変わっていて、瓶にエスカンシアドールと呼ばれる注ぎ口を付けて広口のコップに高い位置から勢いよく注ぎ、シュワシュワと泡のあるうちに飲み干します。
伊野さんがスペインの漁港でよく飲まれているこのワインを魚介料理に合わせて紹介すると、生徒たちは「面白い」と感心したそうです。
「そんなに高価なワインではありませんが、ワインのバックグラウンドや、どうしてこのワインを飲んでいるかというストーリーがあると面白いでしょう?ストーリーが生まれるワインが好きです。もちろん五大シャトーやピノ・ノワールにもストーリーがありますが、それとはまた違った地元密着のストーリーがあると、ワインは楽しいですよね」。
伊野さんのワインストーリーを聞いているうちに、湿度が高い日本の夏に是非チャコリーを飲んでみたいと思いました。
ワインの気軽な楽しみ方
「ワインを飲む時には、“こう言う飲み方駄目”というくくりはないと思います。海岸へ出かけた時、15度のアルコールがある飲み物を暑い浜辺で飲むのがつらいと思われれば、ワインを氷で割ってもいいじゃないでしょうか」とワインの気軽な楽しみ方を聞き、伊野さんとワイングラスを交わすと、仲間たちは楽しくなるのだろうなと思いました。
伊野さんの周りは、ワインがあり美味しいお料理があり、色々な楽しい話が飛び交うのでしょうね。
ワインの素敵な楽しみ方
「今日は特別というときには、レストランに行って、大切な友人と二人で一本のワインをゆっくり楽しむのもいいと思います。お料理の一皿一皿をワインを合わせていただくと、料理とワインの起承転結を楽しむことができると思います。そんな大人の楽しみ方ができれば、高価なワインを一本、二人でゆっくり楽しむのもステキなワインの時間になるのではないでしょうか」と伊野さん。
ワインと料理のストーリーにはどんな起承転結があるのだろうかと想像しています。
夢
 伊野さんが服部栄養専門学校で講師を始めて14年。講師を始めた頃に教えていた生徒が独立し、レストランのオーナーになり始めています。彼らのお店で酒蔵の人たちと賞味会をしたり、ワインとお料理をコーディネートしたりして、常に経験を蓄積する機会を持つのが夢だとか。
伊野さんが服部栄養専門学校で講師を始めて14年。講師を始めた頃に教えていた生徒が独立し、レストランのオーナーになり始めています。彼らのお店で酒蔵の人たちと賞味会をしたり、ワインとお料理をコーディネートしたりして、常に経験を蓄積する機会を持つのが夢だとか。
子どもの頃にワインが身近にはなかった伊野さんとは違い、ご自分の息子さんにとってはワインとはいつも周りにあるもので、息子さんと一緒に食事をすると、「お母さんワイン飲めば」と言ってくれるそうです。息子さんが成人したら一緒にワインを飲むのが夢で、子育てが終わったらご自分のサロンを持つのも夢だそうです。ぜひ素敵なサロンを作っていただきたいですね。
最後に伊野さんからメッセージをいただきました。
「話題のレストランが増えましたが、ワインに興味がないシェフやサービスの方がワインを提供していることがあります。料理は料理で美味しいけれど、ワインと共に楽しむには満足できないお店があるのは残念です。最近はお客の方がワインや料理についてよく勉強しているような時代です。調理の方も、料理だけでなく、ワインのことも知らないといけない時代になってきています。ソムリエまかせでいたら、もしそのソムリエがいなくなった時はどうするのでしょうか?」
「ソムリエ呼称試験を受ける方は、ワインをいつまでも好きでいてほしいです。ヨーロッパに行くと、どの国に旅をしてもたいていワインがあります。ワインが発信してくれるものもあり、ワインは常にあるという文化を理解すれば、ソムリエ試験の勉強は語学の勉強のようなものではないでしょうか。私も、飲んだこともないワインをどうして覚えるのだろうと思って勉強していたこともありますが、後に旅をしてワインがあると、『そうそう、こういうワイン勉強したよね』と思い出したり、話題が盛り上がることもあります」
伊野さんのお話しを聞き、伊野さんにとってワインは骨の髄のような、ご自分のもとを作り出してくれるものだと話されることに納得がいきました。
友達も、仕事も、色々な国を訪問した時にも、ワインを知らず料理だけを追求していたら、今の伊野さんはなかったのでしょうね。
伊野さんが地方を旅すると、お酒を造っている人たちやワイナリーの人たちが伊野さんをゲストとして招きます。飲み物(お酒)を知らなかったら、こんな機会はなかったのかもしれませんね。伊野さんの人生の道のりには、ワインはなくてはならないものだったのですね。ワインが豊かにしてくれる人生があるのだと、伊野さんのワインと人生のつながりに感銘しました。
| プロフィール |
|---|
|
伊野 由布子(いの ゆうこ) ワインアドバイザー、料理研究家。仏のフェランディ校留学の後、「ジャマン」等にて研修。 著書 |
第12回 山田久扇子さん
レストランのためのワインをコーディネートしたり、ワインジャーナリストとしての活動をしながら、ピアニストでもある山田久扇子さん。この2月27日の総会において社団法人ソムリエ協会の理事に就任し、さらにその活躍の範囲を広げられた山田さんに、ワインとの出会い、ピアニストとしての仕事とワインの仕事、ワインと共にある人生について、お話をうかがいました。
5月の新緑の中を、きらきら輝くロングヘアーで颯爽と現れた山田さん。学生時代は武蔵野音楽大学でピアノを専攻し、今でも幾人かのお弟子さんにピアノを教え、二年に一度ご自分のリサイタルを開いています。舞台上ではコンサートドレス姿がきっと鮮やかなことでしょう。
 現在、レストランのためのワインコーディネートをはじめ、ワインレクチャー、ワインに関する執筆など、ワイン関連の仕事を積極的にされている山田さん。彼女がワインの仕事をするようになったのは、ご実家が酒問屋であったこともありますが、「ワインアドバイザーであり、ピアニストである山田久扇子さん」に至るまでには二度の転機があったそうです。
現在、レストランのためのワインコーディネートをはじめ、ワインレクチャー、ワインに関する執筆など、ワイン関連の仕事を積極的にされている山田さん。彼女がワインの仕事をするようになったのは、ご実家が酒問屋であったこともありますが、「ワインアドバイザーであり、ピアニストである山田久扇子さん」に至るまでには二度の転機があったそうです。
山田さんは幼い頃よりピアノの先生になる夢を持っていました。2歳7ヶ月の時、先にピアノを習っていたお姉さんを迎えに行くお母さまについていくうちに、ご自分から「ピアノを習いたい」と言い出し、そのとき芽生えた情熱はついにピアノの先生になる夢をかなえたのです。
中学生の頃から音楽大学でピアノを学ぶことを決心し、晴れて合格。しかしその後、最初の壁にぶつかります。これまでは学校行事ではいつもみんなの中から選ばれて壇上でピアノを弾き、常に周囲から注目されていました。しかし音楽大学に通うようになると、学内のオーディションや演奏会などには上手な学生が大勢いたのです。山田さんは初めて挫折を感じたそうで、ピアノへの情熱が冷めてしまいそうになった時期があったとか。それでも4年間、音大生としてピアノを学び、楽しく学生時代を過ごされたというのですから、山田さんの情熱は冷め切ってはいなかったのでしょう。
卒業後、山田さんはご実家には戻らず、ご自分の力で東京での生活を続けることを決心します。しかしピアノの先生としてだけでは生徒さんの数が一定せず、都会暮らしの生計は成り立ちませんでした。そこで、ある広告代理店に社長秘書として就職します。ところが、これまで音楽一筋だった山田さんはコピーの用紙サイズやFAX送信などの経験さえなく、事務職には全く不慣れでした。
「これまでの音楽をすべてやめてOLとして一からやり直すべきか。もう一度自分の音楽の道を歩いてみるか」
ここで山田さんは大きな決心をします。「バッハの平均律48曲をすべてマスターしよう。それができたら音楽を続けよう」
バッハの平均律48曲は、音楽大学時代、たいていの生徒はレッスンで何曲かはマスターするそうですが、この大曲をすべて弾くことができるのはまれだとか。
会社に勤務をしながら48曲をマスターした山田さんは、再び自信を持って音楽と関わっていくことになります。「ピアノで生きていけない場合」を仮定し、色々なことに挑戦してみた20代の転機でした。
 ワインの仕事を始めるようになった第二の転機は、生涯忘れる事の出来ない魅惑のワインに出会った20代後半の頃です。
ワインの仕事を始めるようになった第二の転機は、生涯忘れる事の出来ない魅惑のワインに出会った20代後半の頃です。
音楽はもちろん、お料理やお花などクリエイティブなことに興味があった山田さんは、レストランに通ってお店の雰囲気や食事を楽しんでいました。そのころよく通っていたイタリアレストラン“Ristorante Manin”でイタリア・ピエモンテ地方の銘醸ワイン、バローロに出会います。ワインの王であり、「王のためのワイン」と呼ばれているワインです。バローロの魅力に、「このワインの素性を知りたい」と強く惹かれた山田さんは、イタリアのワインを特に好んで飲むようになりました。当時“Ristorante Manin ”のソムリエだった荒井基之氏(現在Vini di Arai ヴィーニ・デ・アライのオーナー)に、「山田さんは、一次試験さえ受かれば二次試験の利き酒は絶対合格する!」と励まされ、ソムリエ認定試験へチャレンジすることになったのです。
音楽大学でピアノを学んでいた時でさえこれほど暗記したことはないと思うくらい、家中のありとあらゆるところにワイン産地の地図を貼ったり、トレーシングペーパーで地図をトレースしたりしながら、ワインに関すること、地理や歴史、ぶどうやお料理など、ソムリエ認定試験に必要なための勉強をしました。
そして1993年にソムリエ認定試験に見事合格。ワインコーディネーターとしての道が開かれたのです。
実家が酒問屋だったこともあり、取得した資格とこれまでの知識や経験を生かし、和食や中華のお店にワインを紹介したり、女性誌などでワインに関する執筆活動を始めました。
特にイタリアワインには造詣の深い山田さんですが、音楽を通じてイタリアの文化に馴染み深かったことからイタリアワインへの関心が高まった、というのが始まりです。イタリアのピエモンテ地方のアルバを訪れたのがきっかけでワインに関わる仕事をしていく中、出会ったイタリアワインの醸造家を訪ねたり招かれたりしているうちに、気がつくとイタリア全州を訪れていました。
ワインの世界の小さな扉を開いていくうちにいくつもの扉を開いていて、気がついたら大きなワインの世界に入り込んでいたのです。
「今は、音楽とワインは切り離せないものと信じています。ワインの魅力は、色々なお酒の中でもとりわけ優雅であることです。イタリアでは日々の食卓にワインは欠かせないものになっています。それは音楽も同じ。その点で何か自分の今の仕事に運命的なものを感じます」と山田さん。
「ワインと共にある人生」について尋ねました。
 「色々なシチュエーションで、それぞれの場での楽しみ方が出来るのがワインだと思います。色々な品種があり、色々なタイプのワインがあるのですから。太陽が降り注ぐ郊外での楽しみ方。レストランの素敵なムードの中での楽しみ方。洋食以外にも和食や中華とともにいただく楽しみ方。食事とワインの楽しみ方を知るのと知らないのでは、特にワインがお好きな方でしたら天と地ぐらい違うと思います」とのこと。
「色々なシチュエーションで、それぞれの場での楽しみ方が出来るのがワインだと思います。色々な品種があり、色々なタイプのワインがあるのですから。太陽が降り注ぐ郊外での楽しみ方。レストランの素敵なムードの中での楽しみ方。洋食以外にも和食や中華とともにいただく楽しみ方。食事とワインの楽しみ方を知るのと知らないのでは、特にワインがお好きな方でしたら天と地ぐらい違うと思います」とのこと。
「飲みすぎてしまって会話のムードを壊すことや、健康を害することは避けてほしいです。でも、毎日適量のワインは健康に良いという報告が出ているのですから、ワインを飲める方には良いものです。これから先もずっと付き合っていきたいですね」。
マナーを守って、健康的にワインを楽しんでいきたいと私も同感しました。

山田さんに、女性がワインを楽しむときのマナーについてお尋ねしました。
「女性はワイングラスに口紅が付いてしまうので、ワインをいただく時には薄い色の口紅にします。また、グラスの飲み口は一箇所に決めておきます。グラスの底にブランドマークがありますので、そのマークが常に自分の方向に向くようにグラスを置けば、飲み口を一箇所に定めやすいです」
なるほど、口紅の色まで考えるとはさすがです。
レストランやバーでのワインの選び方についても素敵なヒントをいただきました。
「ワインの仕事をしていると、ご一緒にワインをいただく方々が頑なになってしまわれることがあります。私に一方的にワインリストを押し付ける方、逆にワインリストを取り上げてすべて決めてしまう方がいることもあり、一緒にワインを楽しむことは難しいなと思うことがあります。どちらか一方がワインを選ぶのではなく、例えば『最初のシャンパーニュは私にまかせてください。その後は君にまかせます』と言っていただくと、ワインを選ぶところから共に楽しめると思います」。
山田さんとグラスを交わす方々は、幸せなワインを楽しくいただけるのでしょうね。
ワインの仕事とピアニストの仕事を両立させていらっしゃる、そして素敵な女性として憧れの生き方をされている山田さんですが、これまでの道のりは順風満帆ばかりではなかったそうです。「ワインは、なにしろ覚えるのが難しいです。また値段が高いワインもありますから、経済的な面も含め、色々な場面でハードルがあります。女性は特に『ワインについて知ったかぶりする人は気に食わない』と言われるなど、なんらかの障害があります。でも、そのハードルをひとつ越えると、また違う世界が広がります。イタリアワインをあまりにも追求し、他の国のワインを飲むと具合が悪くなるなど、自分を追い込んだ時期もあります。今は違う国の人の話を色々聞くうちに違う世界も開けてきて、色々なワインとお付き合いしています。楽しいこともあればいやなこともありましたが、一つ一つハードルを越えて次の扉を開いていくことで、新たな世界、新たな自分を発見します。
ワインは自分に取り込めるファクターが多いと思います。農業、気候、地形、歴史など、沢山のファクターはどれ一つとっても面白いです。旅行が好きでワインに興味がある方には、ワイナリーと観光地が一緒になっているところを訪問する旅は、何倍も楽しいものになるでしょう。投資としての位置づけを調べていくのも面白いでしょうね。日本ではまだ免許の関係上なかなか難しいと思いますが、アメリカやイギリスではすでに投資の対象になっています。私の周りでは、ワインがきっかけで結婚されるカップルもいます。ワインを通じて色々なことが人生につながっていくのです。最初に開いたワインの世界の扉は小さくても、その先に広がる道のりには隠れた扉もあれば、なにか人生の転機となる扉もあります。ワインに興味を持たれたのであれば、とにかく興味を持続させて、人生の迷路の扉を開いていってほしいですね」。
山田さんもそうやって、これまで色々なハードルを越えて、人生の迷路の扉を開いていらしたのでしょうね。
 「ずっと追いかけて、いつまでもつかまえられないワインの世界。私はワインへの趣味が仕事に展開しましたが、仕事を超えてこれからもずっと付き合っていきたいと思っています。ワインの仕事としても成功させていかなくてはいけないですし、自分もワインの勉強や仕事に対しさらに努力を続けていかなくてはいけません。とにかく健康で、豊かな気持ちでワインのある人生を過ごしていきたいです。自分が年を重ねた時にどんなワインを飲んでいるかしらと考えると、これからの人生も楽しみでしょう」
「ずっと追いかけて、いつまでもつかまえられないワインの世界。私はワインへの趣味が仕事に展開しましたが、仕事を超えてこれからもずっと付き合っていきたいと思っています。ワインの仕事としても成功させていかなくてはいけないですし、自分もワインの勉強や仕事に対しさらに努力を続けていかなくてはいけません。とにかく健康で、豊かな気持ちでワインのある人生を過ごしていきたいです。自分が年を重ねた時にどんなワインを飲んでいるかしらと考えると、これからの人生も楽しみでしょう」
と、ワインのある人生について情熱的に語る山田さんから、私自身も勇気を持って人生の迷路を進み続けなくてはと、励まされたようです
| プロフィール |
|---|
|
山田久扇子(やまだ くみこ) 静岡県出身。 |
第11回 脇屋 友詞さん
中国料理界で“ヌーヴェル・シノワ”の旗手として著名な脇屋友詞さん。オーナーシェフとして務める赤坂「Wakiya 一笑美茶樓」(わきや いちえみちゃろう)にて、ワインとの出会いや中国料理とワインについて、お話を伺いました。
初めてのワイン
 初めてのワインは赤玉ポートワイン。子どもの頃、お正月になると、いつも振舞い酒として、“赤玉ポートワイン”があり、「なんとなくですが、お正月だけワインが飲めるのだ」と楽しみにしていたそうです。
初めてのワインは赤玉ポートワイン。子どもの頃、お正月になると、いつも振舞い酒として、“赤玉ポートワイン”があり、「なんとなくですが、お正月だけワインが飲めるのだ」と楽しみにしていたそうです。
脇屋さんがワインを好きだと思ったのは、料理の仕事をして何年か経ってからのこと。幾度かワインを飲む機会があった脇屋さん。立川リーセントパークホテルで仕事をしていた時、そこのハウスワインだったドイツワインを飲み、
「甘くてとても美味しいワインだと思いました。ワインというのは、こういう飲みやすくて美味しいものなのだなぁ」と初めて思ったとか。
それからは、甘い味のもの、酸味のあるもの、そして深い味わいのするワインなど、脇屋さんはさまざまなワインに興味を持ち始めます。
脇屋さんがワインに興味を持ち始めたのは、初めて中国料理の総料理長になった27歳の頃。当時、中国料理はほとんどが大皿で提供されていました。少人数で食べられる料理の種類があまりにも少ないことに脇屋さんは疑問を持ちます。「たとえお客様が一人で来店したとしても、前菜からデザートまで適量をゆっくり楽しんで欲しい。中国料理も一人一皿ずつフランス料理のようにサービスしたい」という願いを持った脇屋さんの中国料理は、伝統的な上海料理をベースに、一つ一つを小皿に美しく盛り付けるスタイルになりました。
そして、同じホテルにいたソムリエに、「中国料理にワインはどうだろうか?」と尋ね、ロゼ・ワインをメニューに取り入れたり、同じホテルにあるフレンチ・レストランのセラーから色々なワインを持ってきて、中国料理とワインを合わせてみるなど、豊かな発想でさまざまな試みを続けてきました。
初めはワインをボトルで注文するお客様は少なかったようですが、脇屋さんの中国料理は小皿に少しずつサーヴされるので、お客様も「グラスでワインを一杯いただきたいわ」と、中国料理とワインの組み合わせに、さほど抵抗はなかったようです。初めてのワインは赤玉ポートワイン。子どもの頃、お正月になると、いつも振舞い酒として、“赤玉ポートワイン”があり、「なんとなくですが、お正月だけワインが飲めるのだ」と楽しみにしていたそうです。
脇屋さんがワインを好きだと思ったのは、料理の仕事をして何年か経ってからのこと。幾度かワインを飲む機会があった脇屋さん。立川リーセントパークホテルで仕事をしていた時、そこのハウスワインだったドイツワインを飲み、
「甘くてとても美味しいワインだと思いました。ワインというのは、こういう飲みやすくて美味しいものなのだなぁ」と初めて思ったとか。
それからは、甘い味のもの、酸味のあるもの、そして深い味わいのするワインなど、脇屋さんはさまざまなワインに興味を持ち始めます。
脇屋さんがワインに興味を持ち始めたのは、初めて中国料理の総料理長になった27歳の頃。当時、中国料理はほとんどが大皿で提供されていました。少人数で食べられる料理の種類があまりにも少ないことに脇屋さんは疑問を持ちます。「たとえお客様が一人で来店したとしても、前菜からデザートまで適量をゆっくり楽しんで欲しい。中国料理も一人一皿ずつフランス料理のようにサービスしたい」という願いを持った脇屋さんの中国料理は、伝統的な上海料理をベースに、一つ一つを小皿に美しく盛り付けるスタイルになりました。
そして、同じホテルにいたソムリエに、「中国料理にワインはどうだろうか?」と尋ね、ロゼ・ワインをメニューに取り入れたり、同じホテルにあるフレンチ・レストランのセラーから色々なワインを持ってきて、中国料理とワインを合わせてみるなど、豊かな発想でさまざまな試みを続けてきました。
初めはワインをボトルで注文するお客様は少なかったようですが、脇屋さんの中国料理は小皿に少しずつサーヴされるので、お客様も「グラスでワインを一杯いただきたいわ」と、中国料理とワインの組み合わせに、さほど抵抗はなかったようです。
中国料理の世界へ
 脇屋さんが中国料理の世界に入ったのは、中学校を卒業した15歳。
脇屋さんが中国料理の世界に入ったのは、中学校を卒業した15歳。
脇屋さんが中学2年の時、父親と一緒に東京・赤坂にある山王飯店で会食し、初めて“中国料理”に感動したのがきっかけでした。
「それまでは、チャーハン、ラーメン、餃子しか知りませんでした。だから、こういう“中国料理”があるのだ、こういうところで働きたいな」と思ったのだそうです。
「中学校3年の時。父親が山王飯店に『息子を預かってくれますか?』と頼むと、『本人にやる気があるならばどうぞ』ということで、一年後には、寮に布団と荷物が送られていました」と脇屋さん。
実は脇屋さんが料理人になるきっかけは、子どもの頃にあったようです。父親が作るチャーハンは油っこくてあまりおいしくないと思い、自分でチャーハンを作ってみると、みんなから「とても上手!」と褒められたのです。
「子どもは褒められると調子に乗るでしょ。だから、色々自分で作るようになり、チャーハンにお漬物を入れてみたり、ハムなど色々入れてみました。そしてまた褒められると、うれしかったのです。それで『この子は料理人に向いているから料理の道に行きなさい』という親の勧めもあり、いつの間にかそういう方向に向かっていました」。
脇屋さんの豊かな才能は小さい頃からのものだったのですね。
中国料理とワイン
 ある時、フレンチ・レストラン『シェ・イノ』で、78年のシャトー・マルゴーを飲んだ脇屋さんは、その香りと味わいの奥行きのすばらしさに感動し、後日、オーナー・シェフの井上さんに同じワインを何本か売ってもらいました。「78年のシャトー・マルゴーはびっくりするくらい美味しく、こんな美味しいワインだと、ひと口飲んでお料理をいただきたくなり、そしてまたワインをいただきたくなるのだと感じました」。
ある時、フレンチ・レストラン『シェ・イノ』で、78年のシャトー・マルゴーを飲んだ脇屋さんは、その香りと味わいの奥行きのすばらしさに感動し、後日、オーナー・シェフの井上さんに同じワインを何本か売ってもらいました。「78年のシャトー・マルゴーはびっくりするくらい美味しく、こんな美味しいワインだと、ひと口飲んでお料理をいただきたくなり、そしてまたワインをいただきたくなるのだと感じました」。
脇屋さんは美味しいワインと美味しい中国料理の組み合わせを、もっと多くの人々にすすめたいと思いました。
「中国料理はフランス料理とあまり違いません。たとえば、どちらの料理も鶏を蒸したり焼いたりします。“フランス料理とワイン”との組み合わせが“中国料理とワイン”になると、感じるイメージが違うだけだと思います。自分の作る中国料理には、ソムリエと相談しながら、ワインとの相性を考えています。豚肉の煮込みやフカヒレ等は、普通なら紹興酒が合うというイメージですが、豚やフカヒレのゼラチン質にはブルゴーニュのワインのやさしく複雑な味わいが合うと思います。あまり濃い味のワインだとフカヒレの味が消えてしまうと思います」と分かりやすく解説していただきました。
お話を聞いていると、脇屋さんはフランスワインがお好きなようですが、イタリアやスペインに旅をする際は、その土地のお料理にその土地のワインを合わせて楽しんでいます。料理とワインの組み合わせは、その土地の気候や温度、風土に合わせることも大切で、これは中国茶にもあてはまるとのこと。「中国で気に入った中国茶を買って日本へ持って帰ると、同じ味わいには感じられないことがあります。北海道でいただくラーメンを東京でいただくと、いただく環境の気温が違うので、ラードの味や感じ方が変わってしまい、同じ味わいにならないのと同じことです。その昔、中国では、出してきたお茶と買ったお茶が違うことがありましたが、最近はそういうことはありません。土地の環境の違いが味の感じ方を変えてしまうのです」と、中国茶に詳しい脇屋さんから教えていただきました。
記念のワイン
脇屋さんは1958年生まれなので、58年のワインを見つけて、ご自分のバースディ・ヴィンテージのワインを開けて楽しまれているようです。昨年、双子のお子さんが誕生したので、記念のワインを探すと、まだ市場に出ていないことが判かりました。いつかお子さんのバースディ・ヴィンテージを買いたいと脇屋さん。どんなワインを探されているのでしょうね。
脇屋さんが香港の中国料理店でワインを飲んだ時、中国料理とワインがこんなに合うのだと改めて感動したそうです。そのワインは値段が十何万円と高価なものでしたが、状態はよく、とても美味しかったと、語ってくれました。
中国料理とワインを合わせる時には、毎回そんな高価なワインというわけにはいきませんが、たまにはそんな貴重な機会があればいいですよね。
中国料理とワイン
 脇屋さんが勧める“中国料理とワインの選び方”をお聞きしました。「人数が多い時は、たくさん飲みたい人もいるでしょうから、リーズナブルで美味しいワインをいくつか頼んではいかがでしょうか。二人で食事の場合は、ちょっといいワインを一本。お財布の都合もあると思いますが、シャンパンをグラスで頼んで、あとは美味しい赤ワインをボトルで一本頼む。特に男性と女性が二人で食事をされる時には、男性が少しリードして女性にワインを選んであげたり、女性の好みを聞いてあげるのがいいと思います。お二人ともワインについて詳しい時は相談しながらでもいいのではないでしょうか。たまには値段も見ながら(笑)。女性もワインに興味を持つことは良いことと思います。ただ、あまり能書きを言われると困ってしまいますね(笑)。ソムリエに相談するのもいいでしょうね。探す楽しみ、訊く楽しみがあると思います。中国料理は味わいがさまざまで、さっぱり味の前菜から始まり、濃い味のメインに移っていくため、味わいのバランスを考えてワインを選んでみてください」。
脇屋さんが勧める“中国料理とワインの選び方”をお聞きしました。「人数が多い時は、たくさん飲みたい人もいるでしょうから、リーズナブルで美味しいワインをいくつか頼んではいかがでしょうか。二人で食事の場合は、ちょっといいワインを一本。お財布の都合もあると思いますが、シャンパンをグラスで頼んで、あとは美味しい赤ワインをボトルで一本頼む。特に男性と女性が二人で食事をされる時には、男性が少しリードして女性にワインを選んであげたり、女性の好みを聞いてあげるのがいいと思います。お二人ともワインについて詳しい時は相談しながらでもいいのではないでしょうか。たまには値段も見ながら(笑)。女性もワインに興味を持つことは良いことと思います。ただ、あまり能書きを言われると困ってしまいますね(笑)。ソムリエに相談するのもいいでしょうね。探す楽しみ、訊く楽しみがあると思います。中国料理は味わいがさまざまで、さっぱり味の前菜から始まり、濃い味のメインに移っていくため、味わいのバランスを考えてワインを選んでみてください」。
お料理が美味しい時にはお酒も進み、お料理が進むにつれ、次から次へお酒を頼まれるお客様もいらっしゃるとか。そんな時は料理を作る方もうれしくなってくるそうです。
「お酒の注文が入ったと聞くと、どんなものを飲んでいらっしゃるのだろうと興味が出ます。サービスをする方も、お客様が気に入ってくださっている様子を拝見するのはうれしいことです」とにっこり。
これからの夢
調理場に立つ以外は、料理番組の出演、調理師学校の講師や講演会などで、若い料理人の育成のため精力的に活動している脇屋さん。これからの夢についてお聞きしました。
「少し前までは、中国料理というと中国人が料理長で、トップは中国人と決まっていました。しかし今は、日本人でもトップになっているところが増えています。フランス人にも受け入れられる、日本人によるフランス料理があるように、日本人による、すごく高度なテクニックで作る中国料理を、世界の人たちにも喜んでもらえるよう作り続けていきたいです。それにはお酒、ワインは必要なものと思います。中国料理とワインを合わせて、世界の人々に楽しんでもらいたいです。私も、世界の人たちに認めてもらえ、楽しんでもらえるような中国料理を作りたいです。アメリカでチャイニーズというと、『え、チャイニーズ・・・』といわれるように、中国料理はまだまだ格の低いイメージがあります。チャイニーズも、“中国料理とワイン”でお客様の接待もできるのだという、高度なテクニックで作られる中国料理のイメージを確立したいです。ぜひ世界の人に“中国料理とワイン”が浸透してほしいと願っています」と脇屋さんは情熱的に語ってくれました。
家ではほとんど料理はしないという脇屋さんですが、一年に一度くらい、料理をします。そしてソムリエに選んでもらった、リーズナブルで美味しいワインを飲むのだそうです。脇屋さんが自宅で作るのは鍋料理。日本の鍋料理と違い、「ジャン(醤)」を使った鍋です。中国料理で使う材料で味をとったスープを用意し、野菜やバラ肉を入れていただきます。これがワインにもすごく合うとのこと。どんなお鍋か興味津々です。
脇屋さんに、ワイン村の読者へメッセージをいただきました。
 「ヘルシーな和食ブームは世界的に根強いですよね。だからこそ僕はそろそろチャイニーズの時代がやってくると思います。世界中どこでもチャイナタウンがあるように、これから中国料理とワインの組み合わせの可能性もどんどん広がっていくのではないでしょうか。ワインの造り手にもこの素晴らしいマリアージュを、是非僕の店で楽しんでいただきたいですね」。
「ヘルシーな和食ブームは世界的に根強いですよね。だからこそ僕はそろそろチャイニーズの時代がやってくると思います。世界中どこでもチャイナタウンがあるように、これから中国料理とワインの組み合わせの可能性もどんどん広がっていくのではないでしょうか。ワインの造り手にもこの素晴らしいマリアージュを、是非僕の店で楽しんでいただきたいですね」。
脇屋さんにとって、ワインとは人間と歴史みたいなもの。
「ワインにも歴史があります。それからワインには、人と同じように色々な個性があります。人との出会いのように、ワインにも出会いがあります。
これまでもこれからも、人には色々な出会いがあるように、失敗のワインに出会うこともあるかもしれませんが、喜びのワインと出会うこともあり、まるでドラマのようです。この人と出会ったおかげで色々な世界が広がっていくというように、このワインに出会ったおかげで、人生が広がることもあるでしょう。お酒を飲みすぎるのはいけませんが、お酒はその場を陽気にし、楽しくしてくれる、すてきなものだと思います」と、ワインから人生哲学を語ってくれました。
こんな素敵なお話を聞いて、私のこれまでの中国料理のイメージは払拭されました。中国料理にワイングラスを傾ける素敵な楽しみ方を、これからも世界に浸透させていってほしいですね。
| プロフィール |
|---|
|
脇屋 友詞(わきや ゆうじ)さん 《信条》 1958年 札幌市生まれ 《著書》 《テレビ》 |
第10回 石井幹子さん
日本のみならず世界各地で照明デザイナーとしてご活躍の石井幹子さんに、ワインにまつわるお話し、そして光とワインについてお話を伺いました。
 ワインがお好きで、20代の頃からワインとの付き合いが長い石井さん。
ワインがお好きで、20代の頃からワインとの付き合いが長い石井さん。
「ワインは不思議ですね。ワインテースティング会に出かけると、必ず同じテーブルの方々と仲良くなります。ワインを囲む間にうちとけ、次にお目にかかったときは、前からずっと知っていたような仲になれます」ワインが、“輪(わ)”して“飲む”、“輪飲(わいん)”と言われるゆえんでしょうか。
「一人でチビチビといただくお酒もありますが、ワインだけはそうではなく、何人かと楽しく飲むお酒だと思います。ワインは話題をどんどん作ってくれますしね」
2005年、名誉ソムリエに就任された石井さん。就任の喜びをみんなで分かち合いたいと、千駄ヶ谷の石井さんの事務所に所員全員を集めて、ワインパーティを催されました。
石井さん自ら、集まった15人のために15本のワインを用意し、くじ引きで一人がサービスを担当するワインを一本決め、軽い白から重い白へ、次に軽い赤から重い赤へ、みんなで少しずつ楽しみました。参加者全員のために石井さんがセレクトしたイタリア、フランス、ドイツのワインが15本ずらりと並べられた姿は、きっと圧巻だったことでしょう。サービスを担当した人がそのワインの感想を述べ、飲みきれなかったワインはそのワイン担当者が持って帰っていいという企画。会場にはヨーロッパの地図を貼り、このワインの産地はここ、あのワインはこちらの産地と言いながら、イタリア、フランス、ドイツワインの違いや好き嫌いなどを、ワイングラス片手に語り合う楽しい会になったそうです。
参加者からは「ワインとは国によってこんなにも違うのですか。また是非このような会をしてください」と大好評だったとか。ワインからそれぞれの文化に触れる機会を持つことができる素敵な会だと思いました。
初めてのワイン
 1960年代、照明デザインの勉強のためにフィンランドに滞在中、初めてワインが美味しいと思ったという石井さん。その頃の日本といえば、赤玉ポートワインくらいしかなく、ワイン売り場も少なかった時代です。クリスマスの時、ディナーでいただいたドイツのフランケンワインがありました。フィンランドでは、ドイツのフランケンワインを“スプリングウォーター(春の水)”と呼んでいるのだとか。フィンランドの冬は寒くて暗く、石井さんの滞在していたヘルシンキでは、みんな春の到来を心待ちにしており、“スプリングウォーター”と呼ばれるフランケンを飲むことで、一足早く春の水をいただけて嬉しかったそうです。
1960年代、照明デザインの勉強のためにフィンランドに滞在中、初めてワインが美味しいと思ったという石井さん。その頃の日本といえば、赤玉ポートワインくらいしかなく、ワイン売り場も少なかった時代です。クリスマスの時、ディナーでいただいたドイツのフランケンワインがありました。フィンランドでは、ドイツのフランケンワインを“スプリングウォーター(春の水)”と呼んでいるのだとか。フィンランドの冬は寒くて暗く、石井さんの滞在していたヘルシンキでは、みんな春の到来を心待ちにしており、“スプリングウォーター”と呼ばれるフランケンを飲むことで、一足早く春の水をいただけて嬉しかったそうです。
フィンランドでは通常、アペリティフ代わりにワインを、その後はシュナップス(アルコール度数の強い蒸留酒)をいただくそうです。石井さんにとってシュナップスは「少々強すぎました」とのこと。
フィンランド滞在の翌年、ドイツに移った石井さん。ドイツでのワインの飲み方は、フィンランドの人々の楽しみ方とまた違っていました。ドイツでは、お昼にあたたかい食事をしっかり取る代わりに、夜はハムやチーズなどの冷たいお料理と黒パンで夕食を簡単に済ませ、それからワインを開けるのだとか。
その後フランスに行く機会が多くなる石井さん。長女の石井リーサ明理さんは、現在フランスで照明デザイナーとしてご活躍中で、石井さんがお仕事でヨーロッパに行く時は、パリのリーサさんの所に寄り、荷物を置いてから出かけられることがほとんどだとか。
リーサさんには「空港に迎えに来なくていいから、いいワインと美味しいものを用意しておいてね、できればシャンパンもお願いね」と言っていらっしゃるそうで、すてきな母と娘のひとときを想像しました。パリには美味しいチーズやパテが沢山売られています。それを買ったり、またリーサさんがお料理を作ることもあり、美味しいものを囲み、親子でシャンパーニュで乾杯し、次に白を開けてと、パリでの時間を楽しんでいらっしゃるそうです。
ワインとの思い出
 フランスのボルドー地方にあるシャトー・ラグランジェに行かれた石井さん。古く荒れていたシャトーを1985年にサントリーが購入し、今ではピカピカなステンレスタンクなど設備が整い、立派なシャトーになりました。「シャトーに入っていくと、なんとも言えない醸造香が漂っていて、これがワインの香りだなぁと思いました。シャトーの前の池には白鳥がいて、静寂で本当に美しいお城でした。お食事では何本もワインをいただきました」と石井さん。ボルドーというと赤ワインが有名ですが、軽やかで複雑味があり、丁寧につくられた白ワインもお好きだそうです。
フランスのボルドー地方にあるシャトー・ラグランジェに行かれた石井さん。古く荒れていたシャトーを1985年にサントリーが購入し、今ではピカピカなステンレスタンクなど設備が整い、立派なシャトーになりました。「シャトーに入っていくと、なんとも言えない醸造香が漂っていて、これがワインの香りだなぁと思いました。シャトーの前の池には白鳥がいて、静寂で本当に美しいお城でした。お食事では何本もワインをいただきました」と石井さん。ボルドーというと赤ワインが有名ですが、軽やかで複雑味があり、丁寧につくられた白ワインもお好きだそうです。
石井さんはフランスのアルザス地方を何度も訪問していらっしゃいます。80年代後半、ドイツのバーデンバーデンに友人を訪ねた時のこと。「食事に行こう」と、気軽に国境を越えてフランスへ食事に行くことがよくあり、アルザスまで食事に出かけたときに、アルザスワインを楽しまれました。その時の感想は「アルザスワインはドイツワインを洗練したような感じ。お食事と合うな」というもの。アルザスでは、ワインヴィラージュを訪ねた楽しい思い出が多いのだそうです。
ヨーロッパには、田舎でもワインと食事を楽しむことができる素晴らしいレストランが沢山ありますが、日本には、美味しい食事が出来ても、それに合うワインを置いてあるところがまだまだ少ないかもしれません。石井さんにワインの思い出をうかがい、いつの間にか私も会話にすっかり引き込まれ、日本料理にはどんなワインが合うのかしら、アルザスワインが合うのではないか、お醤油には赤ワインが合うのではないかなどと、ワインとお料理のマリアージュ談義が弾みました。
普段のワイン
 20年ほど前、知人に勧められて購入した90本入りのスイス製のワインセラーには常にワインが入っているという石井さん。それとは別に12本入りのセラーもお持ちで、そちらにはディリーワインを入れ替えて使っていらっしゃいます。
20年ほど前、知人に勧められて購入した90本入りのスイス製のワインセラーには常にワインが入っているという石井さん。それとは別に12本入りのセラーもお持ちで、そちらにはディリーワインを入れ替えて使っていらっしゃいます。
多忙な石井さんの楽しみは、お仕事を終えた帰宅後に、白ワインをグラス2杯ほどいただくこと。イタリアやフランスの白ワインがお好きです。
ご主人はドイツのフランケンワインがお好みだそうです。ご自宅にお客様がいらっしゃると、フランケン独特のボックスボイテルと呼ばれる丸みを帯びた平たい形のボトルが珍しいこともあり、フランケンワインが開けられることが多いそうです。
「フランスワインだとお料理が大変だけれど、ドイツワインだとお料理は簡単でいいので、助かります」と石井さん。
普段、ご主人はビールとウィスキーを楽しまれることが多いのですが、リーサさんが帰国の際は、石井さんとリーサさんは二人でシャンパーニュを楽しまれます。
「フランスでは『いい白ワインを飲めば、ほっそりする』と言います。また、『いいワインを飲めば、二日酔いでも頭が痛くならない』と言います」と石井さん。
ドイツでは辛口ワインの残糖分が4~9g/リットルという定義になっています。赤ワインは白ワインに比べて渋いので、やや甘口のワインになると、実は白ワインより糖分が多いこともあります。それで白ワインを飲むと、ほっそりすると言われるのでしょうか。甘さを感じても、残糖分が5g/リットルの場合もあるので、一概に残糖分によるものとは言えないかもしれません。白ワインといっしょにいただくお料理は、赤ワインに比べて脂分が少ないレシピが多いからかもしれませんね。
それから、頭が痛くなるのは酸化防止剤が原因の一つともいわれています。
ワインは瓶詰めの際、ほとんどのものに酸化防止剤が添加されます。酸化防止剤は熟成とともに少なくなって消えていくそうですが、若いワインは酸化防止剤が消えきっていないため、どうしても頭が痛くなることがあるかもしれません。いいワインで熟成したワインを飲めば頭が痛くならないのかもしれません。あとは熟睡することでしょうか。
「シャンパーニュ地方では『シャンパーニュは長寿のもと』と言われています。シャンパーニュのオーナーの方々は、ほとんど皆、毎日ドゥミ・ブティユ(ハーフサイズボトル)を飲んでいらっしゃるそうです。特に高齢になってくるとある程度の糖分が脳に必要で、シャンパーニュには必要な糖分が含まれているからではないでしょうか」と石井さんは教えてくれました。
私もシャンパーニュは一番好きなので、うれしいお話しでした。
リキュールの楽しみ
 食後のリキュールをもっといろいろ紹介してほしいというのが石井さんの希望です。田崎真也氏がソムリエコンクールで世界 一になった時、コンクールのテースティングで最後に出たアイテムは、フィンランドのリキュール ラッカ(Lakka)でした。「コケモモの香りがする」と、田崎さんはかなり近いコメントをされていました。
食後のリキュールをもっといろいろ紹介してほしいというのが石井さんの希望です。田崎真也氏がソムリエコンクールで世界 一になった時、コンクールのテースティングで最後に出たアイテムは、フィンランドのリキュール ラッカ(Lakka)でした。「コケモモの香りがする」と、田崎さんはかなり近いコメントをされていました。
その時、日本にはリキュールがそれほど普及していないと石井さんは思ったそうです。
「食 事の後、ほんの少量のリキュールをいただきたいですね。美味しいお食事の後、再びお菓子を沢山いただくのはつらいので、リキュールがいただけたらなと思い ます。また脂っこいものを食べた時、リキュールをいただくと、おなかが落ち着きます。イタリア料理の後にグラッパを飲むのは消化剤としての効果があるから という理由もあります。そういう食後のお酒、特にリキュールの楽しみをもっと多くの方々に知っていただきたいですね」と、素敵なアドバイスを下さいまし た。
日本では、さまざまなリキュールがあること、食後にリキュールを楽しむことがまだあまり知られていないからでしょうか。食後にはデ ザートのお菓子が一般的になってきていますが、ソムリエの方々は、是非食事の後のリキュールの楽しみを多くの方に伝えてほしいなと、私も思っています。
ワインの薦め
 すてきなワインの楽しみ方をされている石井さんに、ワインの飲み方について尋ねました。
すてきなワインの楽しみ方をされている石井さんに、ワインの飲み方について尋ねました。
「ワインを知るには、いろんなものを飲むこと、飲み比べてみることが大事です。その時は必ずラベルをじっくり見てください。ワインの産地、どういう葡萄から出来ているのかに興味を持ってみてください。
絵でも音楽でも、沢山知ることで、良い作品、自分の好きな作品が分かってきます。
ワインも同様で、沢山飲み、比べることで、人生がどんどん楽しく良くなっていくと思います」と、石井さんらしい人生哲学が伝わってきます。
「タバコを吸いながらワインを飲んでほしくはありませんね。シガーであれば食事の後にしてほしいです。それから、ワインテースティングの時には香水は控えてほしいです」
照明デザイナーとしての石井さんに、ワインと照明の関係をお聞きしました。
「なるべく電気照明、特に蛍光灯は消してほしいです。キャンドルライトの下で白ワインをいただくのが一日の最高の締めと思います。
フィンランドはキャンドルの消費量が世界一なんです。日本はまだまだキャンドルの使い方が少ないですね。
フィンランドやヨーロッパでは、11月になるとどんどん日が短くなり、職場では卓上にキャンドルをつけるくらい、キャンドルを使う機会が多いのです。
お家ではお花を飾り、おもてなしはキャンドルでする、という風習です。
日本はキャンドルを家の中で使って楽しむという文化が少ないと思いますが、ご自分の目の届くところや食卓に、是非キャンドルを灯してほしいと思います。
男性はハンサムに、女性は美人に見えますよ。(笑)
蛍光灯の下では赤ワインの色が台無しになります。香りがついたキャンドルが多いですが、それはだめです」
ワインとキャンドルという取り合わせを考えているうちに、ソムリエ協会認定キャンドル!?なんて商品も出てくるとおしゃれだな、と思いました。
米国にはレストラン専門のライティングコンサルタントがいます。しかし日本ではまだそこまでいっていません。
石井さんも、レストランに行くと照明が気になることがあるらしいのですが、お仕事がお忙しく、なかなかレストランの照明に関わることができなくて残念とのこと。
 現在、フル稼働でお仕事をされている石井さん。4月にはサントリーホールでオペラ『トゥーランドット』の舞台の照明を担当。夏にはイタリアで野外オペラの照明。秋にも冬にもイベントがいっぱいです。倉敷や鹿児島、下関、上田城、善光寺での照明のお仕事があり、ラスベガスでの世界照明学会では3時間のセミナーを持たれるとのこと。リーサさんともラスベガスでは仕事で会うのだとか。その時はシャンパーニュを飲みましょう、と計画をされているようです。
現在、フル稼働でお仕事をされている石井さん。4月にはサントリーホールでオペラ『トゥーランドット』の舞台の照明を担当。夏にはイタリアで野外オペラの照明。秋にも冬にもイベントがいっぱいです。倉敷や鹿児島、下関、上田城、善光寺での照明のお仕事があり、ラスベガスでの世界照明学会では3時間のセミナーを持たれるとのこと。リーサさんともラスベガスでは仕事で会うのだとか。その時はシャンパーニュを飲みましょう、と計画をされているようです。
石井さんは、ワインと同じくらいオペラもお好きとのこと。オペラには様々なシーンでワインが登場します。舞台照明の仕事でオペラに関わる機会が多い石井さん。大変なこともあると思いますが、お好きなことに仕事で関わることができて、素敵な生き方と思います。ワイングラスを傾ける楽しみ、光とワインの楽しみ、仕事とワインの楽しみをお聞きして、ワインを通じてさまざまな人生の楽しみ方があるのだなと思いました。
「光と共に、ワインと共に・・・」素敵なメッセージをいただきました。
| プロフィール |
|---|
|
石井 幹子氏 照明デザイナ-。 1938年、東京生まれ。日本のみならずアメリカ、ヨ-ロッパ、中近東、東南アジアの各地で活躍。日本照明賞、東京都文化賞をはじめ、北米照明学会より大賞及び優秀賞を受賞するなど国内外での受賞多数。 |
第9回 ジャン・シャルル・クルーアンさん
フランスの経営専門のビジネススクールHECを卒業後、経営大学院においてMBAを取得。フランスでさまざまな分野の経営に携わってきましたが、1998年、フランス食品振興会(SOPEXA)の日本代表として来日。ワインや食を通じて、フランスと日本をつなぐさまざまな事業や企画の場でご活躍のジャン・シャルル・クルーアン氏より、ワインとの関わりや食への想い、日本での生活を通して考えるワインについてお話を伺いました。
ワインとの出会い
 幼い頃からワインと深く関わりがあるクルーアン氏。お母さまの実家は、15世紀からのワインメーカーでした。生まれて一、二週間した頃から、コトー・デクス・アン・プロヴァンスにある、セザンヌの絵画でも知られるサント・ヴィクトワール山の麓のブドウ畑で育ちました。幼少時代に過ごしたお祖父さまの家はワインカーヴ。1階がセラーになっていて、そこでワイン造りが行われ、2階が住居になっていました。毎日セラーを通って自宅に入るので、生まれた時からワインと共に成長されたのですね。4歳の時にはすでにワインを飲んでいたクルーアン氏は、現在ご自分のお子さんにも、美味しいワインを飲む時は、指先にワインをつけて味わわせているのだそうです。
幼い頃からワインと深く関わりがあるクルーアン氏。お母さまの実家は、15世紀からのワインメーカーでした。生まれて一、二週間した頃から、コトー・デクス・アン・プロヴァンスにある、セザンヌの絵画でも知られるサント・ヴィクトワール山の麓のブドウ畑で育ちました。幼少時代に過ごしたお祖父さまの家はワインカーヴ。1階がセラーになっていて、そこでワイン造りが行われ、2階が住居になっていました。毎日セラーを通って自宅に入るので、生まれた時からワインと共に成長されたのですね。4歳の時にはすでにワインを飲んでいたクルーアン氏は、現在ご自分のお子さんにも、美味しいワインを飲む時は、指先にワインをつけて味わわせているのだそうです。
クルーアン氏のお祖父さまはグルナッシュやシラー、サンソーを使用した赤ワインをメインに造っていました。クルーアン氏が特に好きだったのは、100%シラー種で造るヴァン・ド・ペイ・ワイン(地酒)でした。お祖父さまは2004年に97歳で他界し、現在、そのカーヴではワイン造りは行っていませんが、ワインカーヴと家は、クルーアン氏が引き継いでいらっしゃいます。ちなみにコート・ド・プロヴァンス・サント・ヴィクトワールは2005年にAOCを取得し、赤・ロゼの生産が許されています。ソムリエ認定試験の勉強の際にはチェックしなくてはいけませんね。
SOPEXAのお仕事
1990年から96年までパリ農業祭で全農産物コンクールのワイン審査員を務めていたクルーアン氏。現在はフランス食品振興会の日本代表として、日本で活躍しています。来日のきっかけについて尋ねると一言、「愛です」と。
クルーアン氏は来日前、子供たちを学校へ送迎するためのバス会社を経営していました。その頃、25年間フランスに住み、電話会社に勤務する日本人女性に偶然出会います。そしておつきあいが始まり、結婚。ところが、奥さまは東京転勤を命じられます。どうしようかと悩んでいたクルーアン氏に、友人から日本での現在のお仕事の誘いがあり、バス会社を辞めて1998年に来日。クルーアン氏にとっては、これが二度目の来日となりました。
「妻と共に生活するため日本に来ました。私にとって家族は仕事と同様、とても大切なものです。家族と共に生活できるために仕事をする。それが私の幸せです」
初めて日本を訪れたのは、学生時代の友人を訪ねて関西へ遊びに来た21歳の時。実はその時は、日本があまり好きになれなかったそうです。古い情緒豊かなお寺がたくさんあると思っていたのに、大都市が多く、蒸し暑い中、バスや電車で移動したり、とても大変だったのだとか。卒業後1年間に貯めたお金で訪問した日本ですが、物価は高く、お財布がすっからかんになってフランスへ帰国することとなってしまいました。今では「日本食も温泉も大好き」とお聞きして、私は一安心しました。
好きなワイン
 クルーアン氏にとって、ワインは水のように常に身近にありました。ワインとの付き合いは長いのに、それほど詳しくは知らなかったと言います。というのも、仕事でレストランに行っても、自分が日々飲んできたワインしか分からず、ワインにおける深い文化についてはそれほど詳しくありませんでした。ですから、来日当初は自信がなかったそうです。
クルーアン氏にとって、ワインは水のように常に身近にありました。ワインとの付き合いは長いのに、それほど詳しくは知らなかったと言います。というのも、仕事でレストランに行っても、自分が日々飲んできたワインしか分からず、ワインにおける深い文化についてはそれほど詳しくありませんでした。ですから、来日当初は自信がなかったそうです。
折りしも来日した98年は日本におけるワインブームのピーク時。クルーアン氏がフランスでは飲んだことのなかったものやグラン・クリュなど多種多様なワインが日本へ輸入されていました。そこで少しずつワインの勉強をし、日本に来てから本当のワイン愛好家となりました。
「小さい時は山や森に興味があり、自然科学専攻希望でしたが、結局は経営の学校へ進みました。卒業後は、ファッション関係やバス会社など色々な分野の仕事に従事しましたが、今、ワインに関わる仕事ができて、充実しています」
ワインとの付き合い方
 料理と一緒にワインを楽しむのが好きなクルーアン氏。
料理と一緒にワインを楽しむのが好きなクルーアン氏。
「味わいがしっかりしているものよりも、料理とのマリアージュが楽しめるワインが好きです。ワインの一番の魅力は、料理を引き立て、料理を一層美味しくするということです。ロゼワインが好きで、特に私の生まれ故郷のワイン、プロヴァンスのロゼは大好きです。
特別な日ならば、1964年のシャトーヌフ・デュ・パプを飲みたいですね。私のバースデーヴィンテージで、グッドヴィンテージでもあるからです。ローヌ地方のシャトーヌフ・デュ・パプは、樽香やチーズにあるような複雑でとても良い香りがします。
そのほか、ロワールのコトー・デュ・レイヨンやボンヌゾーのオールド・ヴィンテージワインもいいですね。価格はそんなに高くないですよ。例えば、昨年と30年前とを比べても、それほど変わりません。酸のストラクチャー、複雑な味わいなど、本当に素晴らしいです」
クルーアン氏の好きなワインのお話をお聞きしながら、私も色々なワインの香りを想像してしまいました。
「フランス産ではありませんが、スペインのシェリー酒も好きです。シェリーはフランス料理にあるソーセージの前菜に合わせて、アペリティフの時にいただきます。
とにかく食べることが好きですから、その時のお料理に合わせたワインをいただくのが好きです」
フランスのお料理についても、おたずねしました。
「私は昼に一人でレストランに行くことが多いのです。どうして一人で行くかというと、私はフランス人で、日本の会社で働いている方々と昼食の時間が合わないからです。その時は、レストランのワインリストにある一番安いワインを選びます。そのレストランのソムリエが、そこに来た客が一番頼みやすいワインとしてリストに載せており、そのお店のメニューに合うワインであると思うからです。お客さまと一緒の食事だとそうはいきませんが。私はお昼の時間はゆっくり楽しみます。そして、午後はまたしっかりと仕事をするのです」
自宅でも食事はクルーアン氏が作ります。
「ワインの煮込みを作るときは、手ごろで美味しいワインを一本使います。煮込み料理のために開けたのだから、そのワインを料理と共にいただかなくてはと、お料理をしながら、一緒に飲んでいます。ドリンキング&クッキング&ドリンキング(飲んで、食べて、また飲んで)・・・(笑)。妻は1杯、私は3杯くらいの感じです」
多くの人々と接する機会があるクルーアン氏。人々が集まるような時、おもてなしの時は、普段あまり飲む機会がないジュラやサヴォワのワインなどを選ぶのだとか。
「あまり普段に飲まないようなワインをお客様に味わっていただくと、ワインが会話の話題になり、ワインが人と人との関係を作るようになります。会話が生まれ、会話がはずむようなワインを選びたいのです」
日本のワインと日本でのワインの味わい方
 日本のワインもお好きなクルーアン氏。
日本のワインもお好きなクルーアン氏。
「日本のワイナリーは、最近とても頑張っています。100%日本のブドウで造られたワインが好きです。甲州種100%とか、いいですよね。これからロワールのワインと日本のワインでパートナーシップを組む企画があります。どちらも小さなワイナリーそれぞれが頑張っているのが共通点です」
日本でのワインの楽しみ方、またお料理とワインについてのマリアージュなどについて、ご意見をいただきました。
「醤油を使う日本食なら、ポン酢を赤ワインで割るとか、蟹味噌にワインをちょっと入れても美味しいと思います。私は温泉が大好きなので、きりりと冷えたシャブリを露天風呂で飲むというのもお勧めします」
日本酒もお好きだというクルーアン氏。好きなのは「利き酒」で、色々な日本酒を楽しめる会があったら、是非参加したいそうです。日本酒の中では原酒や、純米酒など、お米の味がする日本酒がお好きなんですって。
メッセージ
 「ワインの世界は未知数です。ワインについては知らなくても、飲めば飲むほど、様々なことに関心をもつようになり、自然に文化のことが分かります。ワインを愛する方は、ワインについて語るほかにも、毎年一度、バケーションにフランスのワイン産地を訪れ、ワイン生産者の情熱を現場で感じることをお勧めします」
「ワインの世界は未知数です。ワインについては知らなくても、飲めば飲むほど、様々なことに関心をもつようになり、自然に文化のことが分かります。ワインを愛する方は、ワインについて語るほかにも、毎年一度、バケーションにフランスのワイン産地を訪れ、ワイン生産者の情熱を現場で感じることをお勧めします」
私も、ワイン産地へ旅する機会があれば、ゆっくりと時間をかけ、ブドウ畑で造り手の情熱を、五感を最大限に使って感じています。
クルーアン氏の人生において、ワインはどんな存在なのでしょうか。
「ワインがなかったら・・・あぁ、生きていけないですね(笑)。私は今の仕事、ワインや食に関わる仕事、日本にいること、すべてが天国と思っています。だからこの天国から落ちないこと(笑)が夢です。お金もうけとかでなく、家族が幸せで、楽しく過ごしたいというのが願いです」
『ワインの楽しみは、天国の入り口への鍵』というメッセージを色紙にいただきました。
私たちも天国の入り口への鍵を、これからもゆっくりと時間をかけて楽しんでいきたいですね。
| プロフィール |
|---|
| ジャン・シャルル・クルーアン氏 フランスの経営専門のビジネススクールを卒業後、フランスの経営大学院にてMBAを取得。通信やファッション、運輸などの仕事に従事し、1990年から1998年までパリ農業祭の全農産物コンクールのワイン審査員も務める。1998年よりフランス食品振興会日本代表となり来日、現在に至る。 |
第8回 中丸三千繪さん
茨城県出身のオペラ歌手、中丸三千繪さん。ソプラノ歌手としてデビュー後、数々の国際コンクールで栄冠を手にし、1990年、第4回マリア・カラス国際声楽コンクール(RAIイタリア国営放送主催)にてイタリア人以外として初めて優勝。2003年、(社)日本ソムリエ協会の名誉ソムリエに就任された中丸さんに、ワインとの出会い、ワインのある人生、その魅力についてお話をうかがいました。
ワインとの出会い
 8歳のころからブドウを育て、ブドウジュースを造っていた中丸さんにとって、ワインとの出会いは、ブドウとの出会いでした。
8歳のころからブドウを育て、ブドウジュースを造っていた中丸さんにとって、ワインとの出会いは、ブドウとの出会いでした。
「実家の周りにはブドウ畑がありました。ワイン用の品種?として日本に初めて入ってきたといわれる“フレドニア“を、3段になった大きな鍋の、一番上の段に入れます。真ん中の段はドーナツ状の空洞になっていて、下の段には水を入れます。鍋を加熱し、蒸気を発生させ、上段のブドウからジュースを取り出します。そのブドウジュースを、熱湯消毒したボトルに詰めます。そうしているうち、ブドウは収穫後3日間ほど経つと、自然と醗酵を始めることに気が付きました。これは甘酒と同じ原理と思い、ボトルの中に砂糖を入れてみました。すると、ブドウジュースは瓶内醗酵を始め、ボトルの口をふさいでいたコルクが飛び出し、中のジュースが噴き出したのです。こんな風に幼いころから醗酵したブドウジュースを飲んでいました。高校生になって東京へレッスンに通うようになり、当時ニューオータニのソムリエだった熱田元会長に出会い、ワインを楽しむようになりました。ニューオータニから、ワインの空瓶を、実家でつくるワインを入れるボトルとして送ってもらっていた頃もあります。18歳から海外へ留学し、その頃からずっとワインを飲み続けています」。
中丸さんにとって、ワインは常にそばにあるものだったようですね。
ボージョレ・ヌーヴォーの時にはワインを樽で買取り、空いた樽はお風呂の椅子にしていた頃もあったとか。お風呂場にワインの香りが立ち込めるのを想像してみました。
ブドウジュースが醗酵する原理に気が付いた中丸さん。幼いころは科学者になりたかったそうです。小学1年生の時、夏休みの自由研究発表で茨城県で一位を受賞。それ以来、学校の理科室を開放してもらい、「なぜ海草には根毛がないのか?」という研究を中学2年生まで続けたのだとか。食塩水の濃度を変えた環境をいくつも作り、酸素を送り、海草を育て、顕微鏡で細胞の観察をし続けていたそうです。また、小さい頃からピアノも習い続けていた中丸さん。お芝居好きで、映画“若草物語”で四女役のエリザベス・テーラーが「もっと鼻を高くしたいわ」と言って、洗濯バサミで鼻をつまむシーンがお気に入りでした。そして、色々な人生を生きてみたいという夢と、ヨーロッパに対する強い憧れを持っていました。それが音楽の世界と一致し、今では世界中を飛び回るオペラ歌手になったのです。
しかし、音楽に限らず、ワインや食はもちろん、飛行機の操縦や、テニス、ゴルフ、スキー、スキューバダイビングほか、さまざまなスポーツをこなし、まだまだやりたいことが沢山あるというエネルギッシュな探究心は、科学者になるという夢もあきらめていません。宇宙へ行って、無重力状態で、筋力が地上の時よりも衰えた状態になった時、どのような声が出るのか試してみたい、という夢のようなお話もしてくださいました。
ワインのある人生
 1986年にデビューし、1987年から海外で生活を始めた中丸さん。最初の家はパリとミラノ、その後リヨン、グラスゴー、アイルランド、ボローニャ、ローマ、ナポリ、フィレンツェ・・・など、一番多いときには世界中に12軒の家があったそうです。現在はイタリアのコモ湖とNYを中心に生活。日本にいらっしゃる間はリサイタルなどで忙しく過ごしていらっしゃいます。
1986年にデビューし、1987年から海外で生活を始めた中丸さん。最初の家はパリとミラノ、その後リヨン、グラスゴー、アイルランド、ボローニャ、ローマ、ナポリ、フィレンツェ・・・など、一番多いときには世界中に12軒の家があったそうです。現在はイタリアのコモ湖とNYを中心に生活。日本にいらっしゃる間はリサイタルなどで忙しく過ごしていらっしゃいます。
以前、5ヶ月間フランスで仕事をした際、稼いだお金を全部ワインにつぎ込んだことがあるそうです。「ギャラはキャッシュがいいか、チェックがいいか、振込みがいいか?」と聞かれた中丸さんは「キャッシュでお願いします」と。
そして、仕事が終わった後、レストランに直行し、そのお金でワイン代を値引きしてもらって、そのレストランのワインリストから同じワインが無くなるまで同じワインを飲み続けたそうです。
「味を覚えようと思ってやってみたのですが、ワインで家が何軒建ったのかしらと、母から言われました。自分でワインを買いに行っていた頃は、地図を片手にお店に行きました。飛行機を操縦する時のように、ワインの生産地と地図の緯度・標高などを見て選ぶのです。みんなには笑われましたが、それでワインを覚えたこともあります」。
探求熱心な中丸さんらしいですね。
フランス、イタリア、アメリカの家にはワインセラーがあり、1500本くらい入っているそうです。知っているレストランにはマイグラスが100脚ほどおいてあるらしく、大勢でワイン会をしても、グラスで困ることはないのだと伺い、「すごーい」の一言!ワインを楽しむ時は、一晩中楽しむこともあるそうです。「先週の月曜日に日本に戻り、土曜日は軽井沢でリサイタル。その前はフィレンツェでリサイタルでした。本番の前の日はセーブして飲まないので、その後の反動が大きいのでしょう。フィレンツェでのリサイタルが終わった後、地中海クルーザーに乗って、シャンパーニュをガンガンいただきました。日本に帰国して、またコンサートだったので、しばらく飲まなかったから、昨日は2人で4本くらい飲んだかしら」と、とても楽しそうに語る中丸さん。
「今度一緒に飲みましょうね」と言われ、私はあまりの嬉しさのせいか、中丸さんの笑顔に酔ったのか、ぽうっとしてしまいました。
ワインを飲みながら食事をすることで人の輪が広がるという中丸さん。ベルサイユ宮殿での英仏政府主催のチャリティ親善コンサートでは、故ダイアナ妃臨席の元、フランス代表として出演されました。コンサートが終わって、宮殿で食事が始まった時のこと。ワイン文化の根付いたヨーロッパにおけるワインに対する考え方と、日本のとらえ方に違いを感じたそうです。
世界でトップクラスのシェフ、アラン・デュカスや、ル・ノートルがお料理をしてくださり、サービスにはパリのトップ料理学校であるエコール・ド・キュイジーヌの学生が600人ほど参加したコンサート後の晩餐会。キッチンのない宮殿では、外にテントを張って料理が用意されたそうです。
お食事もワインも、すべてがチャリティ。送り迎えはプジョーやルノーがしてくれます。
750人くらいの出席者は、ほとんど名前に「バロン(男爵)」と付くブルジョワ級の方々ばかり。そのテーブルに出されたワインは、なんと“ムートン・カデ”。
「え!これはテーブルワインじゃない?ブルジョワの方々がいるような席なのに・・・いいや、待てよ、ワインはさらっと、水を飲むように、これでなくてはけないのだわ!」
と思ったそうです。
 ワインをいただくときに気をつけなくてはいけないことについて、訊ねてみました。
ワインをいただくときに気をつけなくてはいけないことについて、訊ねてみました。
「ワインをいただくとき、私が気をつけていることは、口紅がグラスにつくこと。口紅が付くと、グラスを洗うのも大変です。グラスに付かない口紅があったらと探していたら、知人が口紅をコーティングして落ちにくくするものを見つけてきてくれました。英国のエリザベス女王は、ワインをいただくとき、グラスに口紅を絶対つけないそうです。ワインの知識よりも、そしてブドウの知識よりも、まずはそういう気配りが大事なのではないでしょうか。もし口紅がついてしまったら、ナプキンを使ってグラスから口紅を拭き取るのではなく、グラスを置いた瞬間、周りに気づかれないよう、さりげなく指で拭くようにしてはいかがでしょう。NYのレストランでは、みんな気をつけて、人の視界に入らないように、指でサッと拭いています」。
女性としてワインのいただき方をお聞きしたので、男性についても訊ねてみました。
「男性とワインをいただくときに困るのは、『なんでもお好きなワインを選んでください』と言って、ワインリストを女性に渡されることです。接待された場合は、女性の方は、好きなワインと言われても、お値段の設定に困ります。また、そのワインが相手の好みに合うかどうかわかりません。『どうぞ、どうぞ』 、『いいえ、どうぞ、どうぞ』とワインリストをテーブル越しに行ったり来たりさせる譲り合い精神は、おしゃれではあまりないですよね。そういう光景は日本だけではないでしょうか。もしも男性が選べないなら、ソムリエに頼むのはいかが?分からなければ、ハウスワインを頼むので十分ではないでしょうか」。
ワインと食事を合わせていただくことも大切に思っていらっしゃる中丸さん。
「女性の方々は、男性と食事に行くと、ガツガツ食べてはいけないと思っている方が多いようで、あまり食べないように思います。もっと普通に食事をしてはいかがでしょうか?」
そういえば、女性同士なら“食べ放題”に行くのに、男性と“食べ放題”に行くというのはあまり見たことがないですね。
「女性同士で飲み比べして、ワインを楽しむのはおしゃれだと思いますよ。私はワインをいただく時、きちんと食べるようにしています。あ、それから、沢山ワインをいただくので、白い服をなるべく着ていかないようにしています(笑)」。おしゃれは大切ですが、服装のことを気にしすぎていると、普通にリラックスしてワインを楽しめませんよね。
ご自身も料理をされる中丸さんは、ワインと料理を合わせる事が好きだとか。休みの日は一日中キッチンにいるくらい、和洋中なんでも作られるそうです。海外では食材がないので、フレンチやイタリアンが多いのだとか。ワイン会では、ワインと料理のマリアージュも楽しんでいらっしゃるそうです。
中丸さんが一番好きなワインは、ピノ・ノワール。フランスのブルゴーニュがお好きだとか。日本のワインも好きでプレゼントしていただいたメルシャンの1990年“桔梗が原メルロー”の飲み頃を楽しみに待っていらっしゃるそうです。
そして夢は、将来ブドウ畑を持つこと。
「カリフォルニアのナパかイタリアのトスカーナに畑を持ちたいです。でも北のワインが好きなので・・・そうですねぇ、ブルゴーニュにお嫁さんに行った方が早いかな(笑)」。
 中丸さんにとってワインは“心のなぐさめ”。
中丸さんにとってワインは“心のなぐさめ”。
「ワインにどれだけ救われたでしょう。挫折をしそうになったとき、人生の道に迷ったとき、いつも赤ワインがそばにいてくれました。
ワインを飲みながら、LPレコードをかけ、音楽を考えてきました。そして今の私がいます。もしワインがなかったら、寂しいとか、人間を頼りたくなっていたでしょう。私は常に世界中を移動し、一人でいなくてはいけない仕事をしています。いつも勉強をしていなくてはいけないですし、400ページにわたる譜面を覚え、それを映像として頭に入れていくことをしなくてはいけません。だから一人の時間がすごく大事なのです。そういうとき、ワインだったら供にいることができます。声を出さなければ、ワインを飲みながら、譜面を眺め、勉強もすることができます。だからワインに救われていると思っています。
デビューしたての頃、ものすごく孤独でした。誰も応援に来てくれないこともありました。日本でオペラブームの始まる前のこと。リヨンで一人、暖炉に木を入れて暖めようとしたのに、炎が消えてしまって・・・。でもそこにワインとチーズがありました。お金がない頃は、スーパーで200円くらいのワインを買ってきて、金魚鉢で3回くらいデカンタして飲んだこともあります。だから今はデカンタが嫌いです(笑)。貧しかった修行時代を思い出すからです。パスタも、できれば食べなくてもいいかもしれないです。一生分食べましたから(笑)」。
一人静かにレストランでワインを飲んだり、友達と静かにグラスを傾けるのが好きという中丸さん。エネルギッシュでパワフル、みんながうらやむような華やかな人生を歩まれているイメージがありました。それが中丸さんスタイルと思っていましたが、ワインのような、素敵で魅力的な優しい心の中丸さんのスタイルに感動しました。
声が最高の楽器という中丸さん。故ダイアナ妃は中丸さんのファンでした。
現在チャリティ活動をしているのも、ダイアナ妃が亡くなった1997年、何か一つ彼女の意思を受け継ごうと思い、故高円宮殿下に相談をしたのがきっかけだそうです。自分でやってみてはどうか、と殿下よりアドバイスを受け、21世紀は子供がテーマなので、小児癌の子供たちをできる限りの範囲内で支える活動を続けていこうと思ったそうです。
華やかな印象と、強くて芯のある、深い情熱をもった中丸さんの人生には、黄金の丘から生まれるワインがとても似合うと思いました。
今年の12月には東京で中丸さんのリサイタルがあります。中丸さんの歌声を、ワイン村の仲間のみなさんも、ぜひ聴きに行きませんか?
| プロフィール |
|---|
|
中丸 三千繪さん 桐朋学園大学声科卒業、同大学研究科修了。在学中よりニューヨーク、ザルツブルクに留学。 |
第7回 宮川俊二さん
NHKのチーフアナウンサーを退職後、民放のニュースキャスターを務め、現在はバラエティー番組にも出演するなど、幅広くご活躍の宮川俊二さん。
趣味はお料理とワイン。イタリア料理を習い、ワインスクールに通ってワインエキスパートの資格を取得された宮川さんに、ワインとの出会いや、ワインとお料理にまつわる愉しいお話を伺いました。
ワインとの出会い
 宮川さんのご実家は果樹生産農家で、幼い頃は、家の前に広がるブドウ園の中でボーイソプラノの歌声を響かせていました。自宅には収穫したブドウからできた、いわゆる自家製ワインがあり、子供の頃に味わったワインの記憶は「甘味よりも渋味が強いなぁ」だったそうです。
宮川さんのご実家は果樹生産農家で、幼い頃は、家の前に広がるブドウ園の中でボーイソプラノの歌声を響かせていました。自宅には収穫したブドウからできた、いわゆる自家製ワインがあり、子供の頃に味わったワインの記憶は「甘味よりも渋味が強いなぁ」だったそうです。
大人になって、当時あった“赤玉ポートワイン”を経験。その後、出会ったワインは、イタリアのワインだそうです。
1970年NHKに就職し、岐阜支局でアナウンサーとして勤務していた頃です。当時、イタリアのパスタ“ブイトーニ”はなかなか手に入らないものでした。ある日、宮川さんの先輩が“ブイトーニ”を入手したというので、
「今までのようなベチャベチャになったスパゲッティーではない、コシの強い、おいしいアルデンテのパスタを作ろう!」
ということになりました。
さっそく友人と海岸へ潮干狩りに出かけ、とってきた貝を使って、ボンゴレ・ビアンコを作りました。その時に合わせたワインが、イタリアのキアンティでした。
新鮮なアサリたっぷりのソースが絡んだ、プリプリのブイトーニのパスタのおいしそうな香りを想像しました。
 その後、ドイツ哲学を専門とする友人の影響や、80年代前半になってドイツワインが日本に入ってくるようになったことで、クラシックを聴きながらドイツワインを飲むこともあったという宮川さんですが、後にワインエキスパートの資格を取るほどワインの勉強をするようになるとは思っていませんでした。
その後、ドイツ哲学を専門とする友人の影響や、80年代前半になってドイツワインが日本に入ってくるようになったことで、クラシックを聴きながらドイツワインを飲むこともあったという宮川さんですが、後にワインエキスパートの資格を取るほどワインの勉強をするようになるとは思っていませんでした。
これまでのお仕事の分野や、NHKにいたということもあり、バブル時代とは縁がないという宮川さん。ワインブームでみんながワイングラスをぐるぐる回していた頃、あえてシングルモルトをオン・ザ・ロックで飲んでいたのだとか。しかしハード・リカーはアルコール度数が高いため、少し飲みすぎると、翌日、身体の調子が優れないことがありました。そこでワインを飲んでみると、翌日の体調が良く、それからは食事の時にも、ワインを適量ずついただくことになっていったそうです。
本格的にワインを勉強するきっかけは、ワイン関係の知り合いのパーティに出席し、クイズに参加したときのこと。300人の中で、優勝者は女優の川島なお美さんでした。宮川さんも上位に残ったのですが、チーズについての問題が難しく、
「料理もワインも興味があったが、チーズの分野はなかなか到達できていなかった。さすが、優勝者はちゃんとおいしいものを知っていて、ちゃんとおいしいものを飲んできているのだな。自分はなぜこれが美味しいのか、なぜ美味しくないのか、基本的なことがわかっていない。これはちゃんと勉強しなくてはいけない」
と思ったのだそうです。
ワインスクールの認定試験対策講座を受講し始めたのは、試験の数ヶ月前、2002年4月のこと。
「講座はすでに1月から始まっています。今から受講されるのでしたら、一年間勉強して、来年受験されてはいかがですか?」
とスクールから言われた宮川さんですが、教本を見て、やはり受験することを決心しました。
「いいえ、来年は仕事があって受験できないかもしれないので、今年受験します」。
一ヶ月で教本に一通り目を通し、次の半月で再度目を通し、次の一週間でさらに目を通すという、学生時代の受験勉強法を思い出して挑みました。
試験の一ヶ月前にはワインスクールの模擬テストで90点台をマーク。そして、とうとう“社団法人日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート”に見事合格しました。
それからは、色々な場で常にワインや料理が話題に取り上げられるので、勉強しておいてよかったと思っているのだとか。
ワインのほかにも、イタリア料理を勉強した宮川さん。
「はじめはフランス料理を勉強してみたのですが、ソースや食材や調理法に時間と手間がかかり、仕事を終えて帰宅したとき、ワインと合わせて食事を取りたいと思っても、作れる分野じゃないなと思いました。イタリア料理は日常の料理方法に近く、男の料理としてもいいと思います。イタリアワインが好きなので、妻が仕事に出かけているときなどには、よく料理をします」
得意料理は「アクアパッツァ」。沸騰した水で魚を煮、その旨味と野菜の風味をたっぷり含んだスープ仕立てのイタリア料理の一皿です。
「先日作ったアクアパッツァは最高の出来でした。先程まで生きていたカサゴは身がコリコリと引き締まっていました。どこのお店のものより美味しいと思いました」
もちろんイタリアワインと合わせて、楽しんだのだそうです。
ワインとお料理
 宮川さんがワインを選ぶ時、どんな点を心がけているか伺いました。
宮川さんがワインを選ぶ時、どんな点を心がけているか伺いました。
「どの国、どの年代などから、どんなワインがあるかというような、チャートが描けないといけないと思います。男性も女性も、ある程度ワインを勉強した方がいいのではないでしょうか。最近、グランメゾンではないレストランでも、お値段を書いていないメニューを女性に渡すことがあります。ワインを勉強していれば、ある程度市場価格がわかるでしょうが、勉強していないと、注文したワインの値段によっては、相手に不愉快な思いをさせるかもしれません。逆に勉強をしていると、ワインの価値を考えながらワインリストを読むことが出来、リーズナブルで美味しいワインを探したり、ワインの輸入元が分かったりして、ソムリエを交えて会話が盛り上がります」。
ワイン、そして伝えること
 常に勉強熱心な宮川さん。トゥール・ダルジャンのソムリエによるプロフェッショナルなレストランサービスのセミナーに参加した日の夜、外食先で食前酒を運んできたソムリエに
常に勉強熱心な宮川さん。トゥール・ダルジャンのソムリエによるプロフェッショナルなレストランサービスのセミナーに参加した日の夜、外食先で食前酒を運んできたソムリエに
「“食前酒“はなぜ勧めるのですか?」
と訊ねてみたそうです。しばらく回答に迷っているので、
「最初の答えは、売り上げでしょう。それから、この食前酒の後はどのような展開でワインを勧めていこうか考えられますよね。普段していることを、言葉に箇条書きしてみると、サービスの質が変わると思いますよ」
と話してあげたそうです。
「お店の内装や景色がよく、お料理も美味しいお店は増えました。しかし、サービス面というソフトがまだまだだと思います。お客の側がワインや料理について勉強を始めている時代です。ソムリエもワインの知識だけでなく、サービスする人間としてのテクニックをしっかり勉強してほしいです」。
美味しいお料理はもちろんですが、すばらしいソムリエがいるお店に行くと、すごく幸せな気持ちになりますよね。
TV報道キャスターとして活躍されたの宮川さんから“伝える仕事の基本”について、ソムリエも同じ、というお話を伺いました。「報道キャスターの仕事は、自分たちの知っていることを、誰にでも分かりやすく伝えることです。プロフェッショナルが話すことを、視聴者に分かりやすく伝えるのも仕事です。話す仕事は、音量も十分考慮します。相手に伝わる音量でいいのです。ソムリエにも同様のことが言えると思います。ソムリエがワインをテイスティングして独自で感じたことを、一般の人たちに分かりやすく伝える。それがソムリエの“腕”ではないでしょうか」。
1989年、仕事で、日本の古いミシンをベトナムに贈る活動をレポートしたのをきっかけに、ベトナム応援団の活動を続けている宮川さん。「1994年にベトナムで日本語を教えるボランティアをしました。“経済協力”といいますが、自分が出来る“協力”は、相手に対して何か力を貸して、相手が自立するのを助けてあげることだと思っています。今は工場が出来ましたし、この後何が出来るだろうと考えたとき、“ソフト面”だと思いました。ベトナムにはよい食材があり、中華料理をはじめ、フランス領であったことから、腕のよいフレンチの料理人もいます。しかし、サービス面が不足しています。ベトナム料理店でイタリアのバローロを勧められたり、一流ホテルの朝食バイキングにお寿司とおにぎりが並んでいて、その横にお酢がおいてあるのです。日本人はおにぎりにお酢をつけませんね。そういうソフトの情報を教えてあげたいですよね」。
宮川さんが初めてベトナムを訪れたとき、ミシンを贈るレポートの仲介を勤めた良き友人がいます。去年ベトナムを訪れたとき、ワインに興味がある宮川さんがベトナムのワイナリーを訪問したいというと、その友人が手配をしてくれたのだとか。その時のレポートはソムリエ協会機関誌(『Sommelier』No.83 Page30)に掲載されました。そうして出来た素敵な関係があるので、これからもベトナム応援団を続けていくのだという宮川さん。援助するのではなく、自立を助ける協力が出来るように、そんなすばらしい架け橋としての役割を続けている宮川さんを、私も応援していきたいと思います。
 宮川さんは、ベトナムワインのほかに、日本のワインにも注目しています。世界中に寿司バーが増えていますが、そこに日本酒だけでなく、日本のワイン、特に甲州ワインを置こうという動きがあるそうです。日本食ブームに乗って、日本ワインを応援しているのだとか。
宮川さんは、ベトナムワインのほかに、日本のワインにも注目しています。世界中に寿司バーが増えていますが、そこに日本酒だけでなく、日本のワイン、特に甲州ワインを置こうという動きがあるそうです。日本食ブームに乗って、日本ワインを応援しているのだとか。
日本の外からも中からもワインを見て、みんなにやさしく分かりやすく伝えていこうと努力している宮川さんの優しい笑顔が、とても印象的でした。
| プロフィール |
|---|
|
宮川 俊二さん ・1947年 愛媛県宇和島市に生まれる |
第6回 玉利かおるさん
BS朝日の『ワインの誘惑』というワイン番組をはじめ、ラジオやドラマに出演。キャスター、シンガーソングライター、コラムニスト、ワイン講師など、様々な分野で「伝える」活躍をされている玉利かおるさん。社団法人日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートの資格を持つ玉利さんに、「ワインとの出会い」、「ワインとの思い出」、「ワインと仕事」、「ワインとの接し方」などについてお話をうかがいました。
初めてのワイン
 玉利さんが大学生の頃、初めておいしいなと感じて印象に残っているワインは、ドイツの“マドンナ”(リープフラウミルヒ)だそうです。
玉利さんが大学生の頃、初めておいしいなと感じて印象に残っているワインは、ドイツの“マドンナ”(リープフラウミルヒ)だそうです。
学生たちが焼酎やビールなどを飲んでいる中で、ワインはおしゃれな飲み物でした。
実は、玉利さんがワインに出会ったのは、幼い頃です。
玉利さんのお父様は、山梨県の“マルスワイナリー”でワイン醸造のお仕事をしていましたので、玉利さんが幼いながらに美味しかったと記憶しているのは、“マルスポートワイン”という甘味果実酒でした。小学校1?2年生の時に九州へ移るまでは、樽の匂いとぶどうの香りのする環境で育ったそうです。
日本のぶどう畑の棚は、大人が腰を屈めて歩かなくてはいけないくらいの高さですが、玉利さんのイメージ記憶では、子どものとき遊んでいたぶどう畑の棚は、当時の背丈からすると、とても高かったそうです。
今でも、ワインのテースティングをしていると、ぶどう畑で育った頃の懐かしい香りを感じ、気持ちがほっとするのだとか。
大人になって色々なワインを飲むようになりましたが、なにが美味しいのか全然わからないと思ったことから、本格的にワインを勉強することになったとのこと。資格認定試験を受けるべく、学校へ通い、ワインエキスパートの資格試験にみごと合格しました。その後、文化センターでワイン講師をしたり、シンガーソングライターとしてのデビュー作品となった「バングルバングルの風」という CDを2000年に発売した時には、ワインとコンサートのディナーショーを開催したりと、ワインに関わる活躍を始めるようになりました。
学生の頃より DJ、レポーターのアルバイトをし、沖縄のキャンペンガールとしてモデル事務所に入った玉利さん。もっと話し、伝える仕事がしたい、アンカーウーマンになりたいと思い、上京しました。
取得したワインの資格を生かし、ワインについてのコラムを紙面に連載したり、ワインの番組を受けもつようになります。 BS朝日の『ワインの魅惑』は、毎回多彩なゲストを招き、その人にまつわるワインを取り上げ、チーズなどと組み合わせながらゲストに語ってもらうという番組です。例えば、長野県知事田中康夫さんがゲストの時は、シャンパーニュの“クリスタル”。田中氏の著書『なんとなく、クリスタル』にちなんでのことで、また、長野に新風を起こした“ドメーヌ・ソガ”のメルローと、ボルドーに新風を起こしたといわれる“マロジャリア”のワインを比較試飲しながら、ゲストの人生について語ってもらうということもありました。一回に放送二本分の収録を通じて、ワインの名前は知っているけれど、実際に飲んだことがなかったワインを色々飲むことができたそうです。
思い出のワイン
 昨年、お嬢さんが誕生し、それまでしばらくワインを飲めなかった玉利さん。一年半越しでメンバーを集い、先日、広尾のなじみのレストランで「ロマネ・コンティを飲む会」を開催したそうです。玉利さんにとって、また参加者にとっても初めてのロマネ・コンティを飲む機会でした。
昨年、お嬢さんが誕生し、それまでしばらくワインを飲めなかった玉利さん。一年半越しでメンバーを集い、先日、広尾のなじみのレストランで「ロマネ・コンティを飲む会」を開催したそうです。玉利さんにとって、また参加者にとっても初めてのロマネ・コンティを飲む機会でした。
始めの30分はロマネ・コンティだけで楽しみ、後は違うワインで楽しむという段取りでした。
「ロマネ・コンティとはどんなすばらしいワインなのだろう」と期待していたそうですが、想像以上の時を過ごされたそうです。
最初の40分はロマネ・コンティの撮影会。参加者のみんなは、もし、この1988年のロマネ・コンティの中身がダメになっていても関係ないくらい、ワインを眺めるだけで十分楽しんだそうです。いよいよワインを開けて、一口飲んだ時、涙が出てきてしまった、という玉利さん。もう思い残すことがないくらい、理屈抜きにすばらしいワインだったのだとか。一度でいいから飲んでみたいと思っていたロマネ・コンティ。会場の雰囲気を作ってしまう1988年のロマネ・コンティは、まだ少し若い感じもありましたが、とてもきれいなワインだったそうです。
ワインとの接し方
 ワインは場の雰囲気を変えてくれる、という玉利さん。「ワインを囲むと、そこに絶世の美女がいるような気がするのです。すてきな人と一緒にいる瞬間だから、このひと時を大切にしようと思います」。
ワインは場の雰囲気を変えてくれる、という玉利さん。「ワインを囲むと、そこに絶世の美女がいるような気がするのです。すてきな人と一緒にいる瞬間だから、このひと時を大切にしようと思います」。
ワイン会も主催する玉利さん。ワイン会の日は、朝から緊張して挑むのだとか。「まず洋服選びから始めます。どんな洋服にしようか、それが楽しみで、『こういうワインをこういう人たちとこういう場所でいただくのだから』と考えるのがとても楽しくて、その時を大事にしています。洋服の次は、どんな靴をはいていこう、どんなおしゃれをしようかしらと悩みます。靴なんてテーブルの下にかくれてしまうけれど、せっかくワインを飲むのだから、ワインに敬意を払って、頭の上から足のつま先まで、とにかくきれいでいたいと思います。おいしいワインと過ごす時間は、素敵な男性または女性と過ごす時間のようなものなのです。ワインと食事を楽しむときは、おしゃれをしたいですね」
という玉利さんのファッションセンスは抜群で、真っ白な上下のスーツがとてもお似合いです。玉利さんのファッションは、ワイン会同席者のもう一つの楽しみになるのではないでしょうか。
「アメリカのワイン雑誌『ワイン・アンド・スピリッツ』の編集長が、“クォリティ オブ タイム”と書いていました。つまり時間の質が大事ということですね。ワインは質の高い時の過ごし方を与えてくれます」と、玉利さんはきらきらした瞳を輝かせて語ってくださいました。

ご主人はあまりワインを飲まないそうですが、玉利さんの影響を受け、コレクターとしてワインを購入しているそうです。ご自宅には、ご主人が集めている銘醸ワインと、イタリアワインのサシカイヤをはじめ、玉利さんの好きなワイン、そして日本のワイン、旅に出た時に買ってきた地元のワインなどが入ったセラーをお持ちとのこと。
一昨年はシャンパーニュ地方とブルゴーニュ地方を訪れ、三年前はオーストラリア、四年前にはイタリアへ旅をした玉利さん。
「ワイナリー訪問の時は、とても幸せでした。“食べること、飲むこと、選ぶこと”がわかったら、旅が10倍楽しくなると思います。それもワインを勉強したきっかけの一つかもしれないですね」。
近いうちにカリフォルニアのナパ・ヴァレーにお嬢さんを連れて行きたい、という玉利さん。家族でワイン・トレインに乗りたいのだとか。
お嬢さんのお名前はワインにちなんで、「杏珠(アンジュ)」と命名。バースデーヴィンテージとなる2004年のワインの購入は考え中で、市場にはまだ出てきていませんが、一緒にワイングラスを傾けるのはいつでしょうか。
きっとお二人でチャーミングにおしゃれをして、すてきな時を過ごすのでしょう。時間の質、おしゃれなワインを是非お嬢さんに伝えてあげてください。
そしてこれからも、ワインのつくるすばらしい時を、多くの人々に伝えてほしいと思いました。
| プロフィール |
|---|
|
玉利 かおるさん 鹿児島出身 熊本大学卒 |
第5回 山本益博さん(後編)
前回に引き続き、山本益博さんのお話を伺います。マスヒロさんは料理評論家ですが、料理評論家の仕事を始めたきっかけは何だったのでしょうか?
お仕事のきっかけ
 「好きこそものの上手なれ」といいます。ソムリエの方も、ワインが好きで、そういう人こそ良いソムリエになることが多いのかもしれません。「食べることが好きだから、これを仕事にできないかなと思った」と言うマスヒロさん。
「好きこそものの上手なれ」といいます。ソムリエの方も、ワインが好きで、そういう人こそ良いソムリエになることが多いのかもしれません。「食べることが好きだから、これを仕事にできないかなと思った」と言うマスヒロさん。
そのためには何をしたらいいのか?を考えていたそうです。
1972年、出版されたばかりの辻静雄の『パリの料亭』を駿河台下の三省堂書店で手に取ったマスヒロさんは、何度も何度も読んで、ほぼ暗記したといいます。
「その日の夕方、私はひとりでレストラン・ラセールの隅のほうに席をとってもらい、うららかな初夏の星空を眺めながら、サン・ルイのグラスにボージョレをついで、ちびりちびりとやっていました。もうすぐボーイさんがもってきてくれる鴨のオレンジ煮を心待ちにしながら、ついさっき食べ終えたウナギのパテの、シャブリとよく合うのに満足して、すっかりいい気持ちになっていたのです。(『パリの料亭』辻静雄 より抜粋)」
冒頭数行の文章に引きつけられ、
「サン・ルイのグラスって何?ボージョレって何?」という疑問と共に、「この本に書かれていることと同じ経験をしたい」、「フランスに行きたい」と強く思ったそうです。
 学生の時には落語に夢中だったマスヒロさんは、ご自身の卒業論文で桂文楽を取り上げています。しかし4年生のときに桂文楽が他界し、落語にまったく興味を無くしてしまいました。
学生の時には落語に夢中だったマスヒロさんは、ご自身の卒業論文で桂文楽を取り上げています。しかし4年生のときに桂文楽が他界し、落語にまったく興味を無くしてしまいました。
そのころ家族は北海道に転居しており、自分は東京の大学なので、東京で下宿をすることになりました。学生アルバイトとして道玄坂のガソリンスタンドで働いていた時のこと。お昼になると社員は店屋物を取るのですが、自分は学生でお金が無い。そこで、そこにあった電気釜を貸してもらい、自分でカレーライスを作ったり、鯵の開きを焼いてお昼にしていました。すると、お金を出すから、電気釜飯の仲間に入れてほしいとみんなが言い出し、しまいには所長までが「仕事を早く切り上げていいから、食材を買って来い」と言い出したのです。
それからマスヒロさんは、ガソリンスタンドのみんなのご飯を作ることになりました。ハンバーグの時に即席でソースを作ったところ、なにか面白くないな…と思いました。「ソースを作ったら面白いかも!」と思い、道玄坂の本屋で見つけた婦人画報社から出版されているソースの本を開いてみました。
「ソース・エスパニョール、これだ!」と、早速下宿先の台所でソースを作り、タッパウェアに入れてアルバイト先に持って行きました。
「どこで買ってきたソースだ?」と聞かれ、自分で作ったのだと答えると、皆が絶賛したのだそうです。
ソースの本は誰が著者だろうと、改めて見てみると、あの“辻 静雄”とあるのです。
巻末には辻静雄と、ホテルオークラ総料理長の小野正吉とのフランス料理の歴史についての対談がありました。フランス料理家の巨匠オーギュスト・エスコフィエをはじめ、フランス料理の歴史が綴られており、それが「とても面白かった」のですって。
マスヒロさんは思いました。「どれだけ食べること、作ることが好きでも、料理を10代からやっている人にはかなわない。職人仕事は体で覚えるものだから…」と。1972年にこれらの本に出会い、フランス料理に興味を持ったマスヒロさんですが、「既に遅いと思った」と言い、「作ることで職人になれないのであれば、食べることで職人になれないか?」と思い始めます。
料理評論家の仕事
お金を貯めて行ったフランス。当時、料理を作る勉強に出かける人はいても、食べる為にのみ行くという人はなかなかいなかったのではないでしょうか。
「フランスに行ってみて、よし!10年がかりでフランス全土を廻ろうと決めました。10年廻ってなにか仕事にならないだろうか?と考えた時、いつも目の前に立ちはだかるのは辻静雄でした。組織も財力もすべてかなわない。そこで考えました。辻静雄ができないことは何かと」。
辻静雄には大勢の生徒がいました。自分の生徒が出す店の批評をすることは考えられないだろう、といった消去法で生まれたのが、日本で初めて味をランキング方式にした『グルマン』です。
 「おそらく日本で一番フランス料理を食べて来た一人じゃないかと思います。4,000食ぐらい食べたでしょうか。『グルマン』を書いていた頃は、人間フォアグラのようになっていました。
「おそらく日本で一番フランス料理を食べて来た一人じゃないかと思います。4,000食ぐらい食べたでしょうか。『グルマン』を書いていた頃は、人間フォアグラのようになっていました。
ガイドを創っている時は壮絶でした。
『取材で来たのか?プライベートで来たのか?』、『書いたものを訂正すると言うまで帰さない』と、監禁状態のこともありました(笑)。今はノルマで食べることはなくなり、30年以来の健康を取り戻しています(笑)。
『なに若造が』、とさんざん叩かれましたし、いまだに叩かれています(笑)
。でも、町のレストランは『いいガイドブックが出版された』と喜んでくれました」。
「出版当時、フランス料理と言えばホテルのフランス料理ばかりが取り上げられ、ホテル以外の店としては“ロオジエ”が一番トップと言われていました。当時のロオジエの社長がこの本を見て、とてもショックを受けたそうです。というのも、街の小さなレストランが詳細に取材されていて、ホテルのレストランは一軒も載っていない。そして、そのロオジエも、一番最後に批評もなしで店名が載っていただけなのですから。社長はその晩は眠れなかったそうです。
それからロオジエの大改革が始まり、銀座八丁目のビルの上から銀座の今の場所に移ってきました。この本がなかったら今のロオジエはなかったと思います。僕は別に今の状況に一撃を加えるなんてことは思いませんでしたけれど…。むしろ、レストランのシェフは常にずっと勉強しているのに、お客さんも勉強しないと進歩しないと思ったのです。お客さんが勉強して、初めてレストランも向上するのです。レストランがどういう反応をするかは二の次だったのです。
食べる人に頑張ってほしい。いつも行きつけの店から見ていくのでなく、その近くにある情報を見て、『こんなお店があるのか!』という感じで、ぱっと光が輝くようになればいいなと思ったのです」。
 「これは日本のワインを造っている人によって書かれた、初めてのワインの本だと思います。ソムリエがワインを評価することがあっても、ワイナリーの人が発言する本はなかなかありませんでした。この本を読んでいるうちに面白くなり、興味を持ちました。しかし、この人たちは料理のことを考えてワインを造っているのだろうかと、疑問を持ちました。世界のコンクールで優勝することを狙ったワインを造っているだけでは、ワインだけが独立して走ってしまうことになります。そこで、『和食で和飲(ワイン)』をテーマにして、人を集めることにしました。ワイナリーの方を囲んで、造り手の情熱を語っていただきます。それから毎日家で食べる食事を頭に浮かべながら、ワインナリーの人にも一緒にワインと食事のマリアージュを経験していただくのです」。
「これは日本のワインを造っている人によって書かれた、初めてのワインの本だと思います。ソムリエがワインを評価することがあっても、ワイナリーの人が発言する本はなかなかありませんでした。この本を読んでいるうちに面白くなり、興味を持ちました。しかし、この人たちは料理のことを考えてワインを造っているのだろうかと、疑問を持ちました。世界のコンクールで優勝することを狙ったワインを造っているだけでは、ワインだけが独立して走ってしまうことになります。そこで、『和食で和飲(ワイン)』をテーマにして、人を集めることにしました。ワイナリーの方を囲んで、造り手の情熱を語っていただきます。それから毎日家で食べる食事を頭に浮かべながら、ワインナリーの人にも一緒にワインと食事のマリアージュを経験していただくのです」。
海外から安くて美味しいワインが輸入される昨今、日本のワインはどうしても太刀打ちできず、消費量が伸び悩んでいます。
「日本のワインがこれから頑張っていくには、1,000円を超えないぐらいのリーズナブルで、毎日飲んでも飽きないワインを造っていくことです」と言うマスヒロさん。
現在の焼酎ブームなど、お酒の流行は10年サイクルで変わります。
日本の同じ土壌からできる農産物と日本のワイン、食事とワインが合わない訳がありません。
毎晩晩酌するときに、日本のワインが食卓に並ぶ日を夢見て、そういうワインを造ってほしいと、日本ワインにエールを送るマスヒロさん。是非日本のソムリエの方々とともに、日本のワインを伝道してほしいです。私も消費者として、日本の食材と日本のワインを改めて見つめ直したいと思いました。
お酒として、歴史が長く、世界中で造られているのはワインしかありません。
超一級品はもちろん良いですが、1本1,000円のワインも一生懸命愛でようと思っているというマスヒロさん。
「ワインの魅力にとりつかれている人には、料理と食事の中にワインがどう位置づけられるか、考えてほしいですし、料理と一緒に飲んで美味しいというワインを、大切にしていってほしいですね。
また、ワインの初心者には、高級ワインといわれるのがなぜ美味しいかを、誰かと一緒に飲む経験をされて知ってほしいです」。
ぽち袋
 ワインの山を再び登っているマスヒロさんは、外食の際、ソムリエには「食事を邪魔しない手頃なワイン」を頼むそうです。
ワインの山を再び登っているマスヒロさんは、外食の際、ソムリエには「食事を邪魔しない手頃なワイン」を頼むそうです。
「合う料理」「合うワイン」というのはいくつでも出てきますし、天井知らずです。
だからあえて「邪魔しない」というのだそうです。
うれしいサービスを受けた時、お店の方に渡す“ぽち袋”を常に手帳に入れて持ち歩いているマスヒロさん。白い和紙の袋で、一つは白い鯛が浮き彫りになっており、もう一つは赤い鯛が浮き彫りになっています。右上に「又来鯛(また来たい)」、その下に「益博」という文字が黒ペンで書かれ、白い鯛の袋には沖縄サミット開催を記念して発行された2,000円札が、赤い鯛には5,000円札が三つ折りにして入っています。
「僕がソムリエに『食事を邪魔しないワインをお願いします』と注文すると、ソムリエは色々考えてくれます。ある時も、とても美味しいワインを出してくれたので、お値段を聞いてみると8,000円のワインだと言います。リーズナブルで、しかも食事と合って、とても美味しいワインだったので、この“ぽち袋”をソムリエに渡しました。彼の心遣いに対する、僕の気持ちなのです」。
日本はサービスに対して対価を払うことをしません。いいサービスを受けたいと願うのであれば、まずお客がサービスに対して、評価をしてあげなくてはいけません。それがマスヒロさんの“ぽち袋”のようです。
マスヒロさんの“ぽち袋”に習って、何人かの方々が同じようにして気持ちを表したデザインの“ぽち袋”を持ち始めているようです。
私もいつか、そういうちょっと素敵な“評価の表現”をできるようになりたいと思いました。
「レストラン側のサービスは、お客の全てをよく見て、お客の話をよく聞き、自分からはしゃべらないことがスマートです。
日本では、女性がワインを選んでいることがありますが、ワインを知っている女性なら特に、全てを知り、全てを味わいながら、つつましやかに『美味しいワインですね』というのがエレガントだと思います」とのこと。エレガントにワインを楽しめるよう、心がけたいものですね。
“Convivialite”
 最後に、ワインを美味しくいただくにはどのようなことを心がけていらっしゃるのかを訊ねました。
最後に、ワインを美味しくいただくにはどのようなことを心がけていらっしゃるのかを訊ねました。
「日本の悪い点は、席に着いてもホストになる人がなく、全員がゲストになってしまうことです。レストランの入り口をくぐるまでは、お客のみんながゲストですが、いったん席に着いたら、必ず一人はホストになります。男性はもてなす側、女性はもてなされる側になります。もてなす側ともてなされる側になってコミュニケーションをするからこそ、美味しいものを愉しくいただくことができます」。
フランス語で“Convivialite”(コンビビアリテ=フランス語で『親しみ』)というのがまさにこのことだと、メッセージをいただきました。
「飲んで、食べて、おしゃべりしてこそ食卓は楽しい」
私も『一緒に食事をして楽しい人』になりたいなと、マスヒロさんの楽しいお話を伺って、強く思いました。
| プロフィール |
|---|
|
料理評論家 山本益博さん(東京都出身、早稲田大学卒) ・1948(昭和23)年に、東京の下町、浅草・永住町(現在の台東区元浅草)に生まれる。 |
第5回 山本益博さん(前編)
『グルマン1984』、『マスヒロの365日食べ歩き手帳』など、"食"に関する著述業の他、講演、テレビ・ラジオ・CM出演、食関係のイベント企画やプロデュース、広告制作などに幅広くご活動されている料理評論家、山本益博さん(以降“マスヒロさん”と呼ばせていただきます)。今回は、マスヒロさんが出会った「食」と「ワイン」に関する思い出や、ワインを「美味しく&楽しくいただく」ためのお話を伺いました。
ワインとの出会い
 マスヒロさんがワインを初めて飲んだのは1973年。フランスに初めて旅をする前のこと。どんなワインを飲んでいいのかわからず、酒屋で勧められたポルトガルのロゼワインを飲みました。ユニークな形の瓶に入った、その少し微発泡したワインがワインとして一般的だった時代でしたが、マスヒロさんにとってそのワインは、あまり美味しいとは言い難いものだったようです。
マスヒロさんがワインを初めて飲んだのは1973年。フランスに初めて旅をする前のこと。どんなワインを飲んでいいのかわからず、酒屋で勧められたポルトガルのロゼワインを飲みました。ユニークな形の瓶に入った、その少し微発泡したワインがワインとして一般的だった時代でしたが、マスヒロさんにとってそのワインは、あまり美味しいとは言い難いものだったようです。
2本目に出会ったワインは、ご家族の転居先、札幌にある酒屋で見つけた1965年の“シャトー・ラトゥール”です。1965年はあまり良くない年とは知ってはいましたが、「5大シャトーのひとつ、ラトゥールなのだから」、と飲んでみたそうです。年のせいもあったかもしれませんが、酒屋の保存状態が良くなかったこともあり、そのラトゥールは渋くて酸化していました。そのとき「これが世界最高峰のワインか・・・」と、マスヒロさんは残念に思ったそうです。
それから10年ほどたって、マスヒロさんは、初めて好きなワインに出会います。
当時、銀座レカンのソムリエ下野氏から、「レカンにいらっしゃるお客様の中で、一番恐ろしいお客様のひとりに、ボルドーのサン・ジュリアンのワインばかりを召し上がる方がいます。ソムリエとして常に良い状態のワインを出していますが、その方がいらっしゃると、本当にいい状態のものしか出したくないと思うくらい、気を遣います」というお話を聞いて、マスヒロさんもできる限りサン・ジュリアンのワインを飲もうと思っていました。パリを訪問中、フランスのホテル・レストラン・ガイド『ミシュラン』と並ぶ『ゴー・ミヨ』に載っていた酒屋さんに出かけたときのこと。そこは、乾物やらジュースやら、なんでも売っているようなお店で、ベレー帽をかぶった70歳くらいのおじいさんが一人でやっていました。
そのおじいさんに、「サン・ジュリアンのワインを探している」と言うと、「地下のワイン倉庫から探してくるので、店番をして待っているように」とマスヒロさんに言い、地下へ降りて行きました。店番をするはめになったマスヒロさんでしたが、しばらくして、おじいさんが持ってきたのは、1960年代の“シャトー・ベイシュヴェル”。それを買って日本に帰り、飲んでみると、とても美味しかったのだそうです。
 しばらくして、再びパリに行く機会があり、そのお店をまた訪れました。ベレー帽のおじいさんはマスヒロさんのことを覚えていて、「今お客の相手をしているから、自分で地下へ降りて行って探してきなさい」と言うのです。地下に降りて行くと、そこは地下1階と2階になっていました。そして年代毎に並べられている訳でもないのですが、いいワインがゴロゴロと積まれています。マスヒロさんは、自分の生まれ年でもある1948年と白墨で書かれた“シャトー・ラフィット・ロートシルト”を見つけました。
しばらくして、再びパリに行く機会があり、そのお店をまた訪れました。ベレー帽のおじいさんはマスヒロさんのことを覚えていて、「今お客の相手をしているから、自分で地下へ降りて行って探してきなさい」と言うのです。地下に降りて行くと、そこは地下1階と2階になっていました。そして年代毎に並べられている訳でもないのですが、いいワインがゴロゴロと積まれています。マスヒロさんは、自分の生まれ年でもある1948年と白墨で書かれた“シャトー・ラフィット・ロートシルト”を見つけました。
お店に上って行き、さっそくおじいさんに「本当にラフィットなのですか?」と訊ねると、
「ボトルを開けたらブション(コルク)にちゃんと書いてありますよ」と言います。
いくらかと訊ねると、約30,000円でした。
日本に買って帰ったマスヒロさんは、ワインの旅の疲れが十分癒えた頃、気の合う仲間と共に、この1948年のラフィットを開けることにしました。「自分と同じ生まれ年の1948年、どのくらい自分と同じだけ熟成しているのか、なおかつ若々しいか、勝負してやろうじゃないか!」と意気揚々とし、自ら、そうっとコルクを開けました。その瞬間、不二家のミルキーキャンディを思わせるような甘い良い香りがしたそうです。
「失礼しました。家柄も育ちも、全く違う、すばらしいワインです!こんなワインがあるのか!」と、ワインの魅力にどっぷり浸かってしまったマスヒロさんでした。
48年はプティットタネ(小さな年=あまり偉大な年ではない)と言われていますが、悪い年ではなく、多くが1960年代に飲まれてしまっているため、1980年代の当時まで残っているのはとても珍しいことでした。おじいさんの地下倉庫で静かに眠りながら時を経て来た『1948年のラフィット』は、初めてマスヒロさんが美味しいと思ったワインであり、本気で一生懸命ワインの勉強をはじめるきっかけとなったワインでした。
それからもちょくちょくその店に出かけてワインを買ってきていたマスヒロさんですが、1985年に訪れたとき、おじいさんがお値段的にもこれがお勧めと出してきたのは、“シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン 1960”で、当時のお値段で10,000円くらいだったそうです。
「1960年も小さな年ですが、むちゃくちゃ美味しかったです。僕は買ってきたワインは全部飲んでしまいますが、忘れられないワインはボトルごと取っておきます。エチケットを外してもいいのですが、これくらい年を経たワインだと、はがす方が困難ですし、瓶の澱ごと取っておきます。このボトルを見る度に、20年前のことが昨日のことのように思い出されるのです。
家にも事務所にも沢山空きボトルがあります。僕の事務所はワインのカビの香りがするでしょう。まだまだワインが生きているのです」と言って見せて下さったのは、なんと1929年のロマネ・コンティのボトルでした。まだわずかに液体状の澱が残っていて、コルクを外すと、何とも言えない甘い魅惑的な香りがしました。
ワインとの思い出
 「フランスのレストランを巡っているとき、ブルゴーニュから100キロほど離れたところにあるレストランのワインリストに1929年のロマネ・コンティを見つけました。当時85年頃で5,000フラン(125,000円)という価格でした」。
「フランスのレストランを巡っているとき、ブルゴーニュから100キロほど離れたところにあるレストランのワインリストに1929年のロマネ・コンティを見つけました。当時85年頃で5,000フラン(125,000円)という価格でした」。
パリにあるベトナム料理店『タンディン』のオーナーシェフで、ポムロールのペトリュスを有名にしたことでも知られるヴィフィアン兄弟と友達のマスヒロさんは、彼らから「1929年のロマネ・コンティを飲まないでロマネ・コンティを評価してはいけない」という話を聞いていたので、1929年のロマネ・コンティをリストに見つけたとき、どうしても飲みたいと思いました。
ワインを買うのであれば、パリのワイン専門店で買うと値段が高いので、昔三ツ星だったレストランの持っているワインをよく買っていたというマスヒロさん。そういうレストランは、三ツ星だった頃に良いワインを沢山仕入れており、当時の価格のままリストに載っていたことが多いのだとか。このときも、「1929年のロマネ・コンティを買いたい」とソムリエの方に頼みました。すると、オーナーからの伝言で「これだけは、飲みたい仲間を連れてきて、ここで飲んでください。戦争中も、ワインを隠すために壁を造ったりして守り続けてきたワインなのですから…」と断られてしまいました。
それから10年が経ち、日本料理店『青柳』の小山裕久さんが、パリのホテル『ブリストル』でフェアを催すことになり、マスヒロさんをはじめ何人かで応援に行くことになりました。そこでこのロマネ・コンティの話をすると、『ブリストル』のフェアでフランスに行くのなら、そのロマネ・コンティのあるレストランにも是非行こうということで、皆が賛同したそうです。ワインリストで見つけてから随分月日が経っていたので、アシスタントの方に1929年のロマネ・コンティがまだあるかどうかレストランへ電話で確認してもらいました。その値段は10年の間に3倍になっていましたが、それでも270,000円で、後2本残っているとのことでした。そのソムリエに、日にちとロマネ・コンティ1本だけを予約し、参加者には当日まで、どこのレストランに行くのか伏せておきました。先を越されて飲まれては困りますものね。
やっとレストランへ行くその日の朝、皆に場所を公表し、車2台に7名が乗り込み、いざレストランへと出発しました。
日曜日のお昼、かつての三ツ星レストランは、年配のお客様が多く、ソムリエは大変緊張してボトルを開けるので、レストラン中で注目の的だったそうです。前菜までいただいた後、メインのお肉料理の前に、一旦お料理をストップしてもらいました。
「1929年のロマネ・コンティとなにかのお料理を合わすなんて、不可能です。そうしていただいたワインは、多少酸化していましたが、初めて見つけたときから10年も経っているのにも係わらず、まだ香りが素晴らしかったです」。
その時の食事では、ロマネ・コンティのほかにも、1940年代、1950年代のボルドーの値段が手頃だったため、皆さんでおいしく飲まれたそうです。
 「本当に狙い目は、1950年代1960年代にかつて三ツ星だったレストランです。現在三ツ星の最先端レストランに行くことも大切ですが、かつて三ツ星だったレストランに行くのもいいものですよ。1985年くらいのことです。サン・テミリオンにある『オテル・ルーバ』に、取材の仕事で泊まりました。驚いたのは、ボルドーなのにブルゴーニュのワインが沢山あるのです。以前はブルゴーニュでソムリエをしていたという給仕係が空けてくれたのが、1949年のコルトンです。ボルドーでこんなワインがあるのか、と感動した思い出のワインの一つです」。
「本当に狙い目は、1950年代1960年代にかつて三ツ星だったレストランです。現在三ツ星の最先端レストランに行くことも大切ですが、かつて三ツ星だったレストランに行くのもいいものですよ。1985年くらいのことです。サン・テミリオンにある『オテル・ルーバ』に、取材の仕事で泊まりました。驚いたのは、ボルドーなのにブルゴーニュのワインが沢山あるのです。以前はブルゴーニュでソムリエをしていたという給仕係が空けてくれたのが、1949年のコルトンです。ボルドーでこんなワインがあるのか、と感動した思い出のワインの一つです」。
ワインと食
 基本的にフランスの赤ワインがお好きだというマスヒロさん。
基本的にフランスの赤ワインがお好きだというマスヒロさん。
「ちょっと生意気に聞こえるかもしれませんが、1980年代以降のワインには興味ないのです。どんなに健康状態が良くても、そのワインが一番飲み頃の時には、僕はもう生きていないかもしれません。醸造長は、今造っているワインが何十年後かに良くなると思って造っています。そのワインの最高潮の時に、醸造長自身ももしかしたら生きていなくて飲めないかもしれないというのに…。なんてロマンティックなんだろうと思いませんか?
だから造り手の気持ちに思いを馳せながら、ワインを飲みたいと思っています。
ボルドーは最低でも30年くらい経ったものが美味しいと思います。いい仲間を集めて美味しいワインを飲めたら、なんてすてきな人生でしょう。今飲んで一番美味しいのは60年代のワインです。1945年も美味しいです。ムートンだったら2020年くらいまでは美味しいのではないでしょうか。45年、47年、49年、53年、59年、61年、66年のワインもいいですね。そういうワインを、みんなで分かち合って飲みたいです。
一本20,000円のワインを一人で飲むより、グラス一杯20,000円のワインをみんなでシェアー(分かち合って)して飲む方がいいです。一人で飲むほどつまらないことはありません。食事もワインも、分かち合う、シェアーするのが魅力だと思います」。
 自分ひとりで楽しむのではなく、みんなで分かち合うことが美味しい。ふるまい酒で飲んで飲んで、ということもあるというマスヒロさん。それでも昔はワインを一滴も飲めず、フランス料理をお水でいただいていたこともあったのですって。
自分ひとりで楽しむのではなく、みんなで分かち合うことが美味しい。ふるまい酒で飲んで飲んで、ということもあるというマスヒロさん。それでも昔はワインを一滴も飲めず、フランス料理をお水でいただいていたこともあったのですって。
「フランス料理を食べ始めた頃は、ワインが飲めませんでした。僕の昔を知っている人は、『マスヒロさん、水を飲んでフランス料理のなにがわかるの?』と言っていましたからね。でもその頃から飲んでいたら、ひっくり返っていたでしょうね(笑)。
ワインが飲めるようになったのは、ひとえに好奇心です。フランス料理はワインがないと分からないと思い、一生懸命勉強しました。勉強すると、一口しか飲めなかったのが、だんだん飲めるようになったのです」。
アロマもブーケもわからなかったというマスヒロさんは、1982、3年くらいから月に3回ほど本気でワインの勉強を始めます。そのうち1回は六本木のワインバー『ミスター・スタンプス・ワイン・ガーデン』の磧本さんのところに、ソムリエやワインを扱っている人が7~8人集まり、テイスティングの勉強をしていました。
新しいワインを並べて、いつが飲み頃か、買う価値のあるワインかどうかを考えたり、造り手によってどう違うか、といった勉強会に一生懸命出かけました。
それとは別に、本当に美味しいワインならお金を出してでも飲みたいという仲間7~8人と、古いワインを買って来ては、毎回4~5本、若いワインから古いワインへヴァーティカルでテイスティングをしたり、また、ヴィンテージものの横綱格ばかりで古いワインの飲み比べをしたりしながら勉強しました。
ソムリエと一緒に勉強していると、なかなか自分の言葉が出せないと思ったマスヒロさんは、月に1回、お寿司屋さんや和食の方など、ワインを飲んでいない人、ジャンルの違う人を集め、マスヒロさんが講師になってワインをセレクトし、一緒に料理を食べながらワインについて話す会を始めました。
覚えた言葉を、本を見ないで人に伝えることで、自分の理解につながっていきました。そして次第に、その会の人々も、いつしか古いワインを飲みたいと言い出すようになったのだそうです。
田崎真也さんが六本木の『ボンヴィヴァン』でソムリエをしていた頃のこと。ワインのテイスティング会で集まっているところへ、ちょうど来日中だった友人の『タンディン』オーナー、ヴィフィアン兄弟の一人がゲストで来てくれました。テイスティングをしていると、一人の参加者が遅れて登場しました。持ってくる時に澱が舞うといけないので、あらかじめ自分のところでデカンタをしたワインを持ってきたと言います。これ幸いと、ブラインド・テイスティングをすると、プロばかり集まっている中で、ヴィフィアンが、「ここ一ヶ月以内に飲んだワインに極めて似ている。1964年のシャトー・タルボではないか?」と言うのです。実はそれは1962年のシャトー・タルボでした。「小説で読むような場面を初めて見ました。彼は職業柄ここ一ヶ月に何百本も飲んでいるはずですが、旅先の日本で、いつもと違う環境にいるのに、年代とワイン名を当てたのです。日本へ運ばれてくる段階でやや年代がぶれたとしても、驚きました。頭で記憶することが、ワインにおいてこれだけすばらしいものを引き出せるのですね」。
「ヴィフィアンは『あらゆるお酒の中で、頭を通過する唯一のお酒はワインだ』と言うのです。畑まで当ててしまうなんて、しかも自分が相手の国に出かけてきたのに、いつもと違う状態にあっても当てることができるなんて…。ワインの底知れない魅力を感じました」。
「頭を通過する」なんて、すごい表現です。私も今度ワインをいただくときには特別意識してみようと、心の中で思いました。
マスヒロさんのお話は次回へと続きます。どうぞお楽しみに!
| プロフィール |
|---|
|
料理評論家 山本益博さん(東京都出身、早稲田大学卒) ・1948(昭和23)年に、東京の下町、浅草・永住町(現在の台東区元浅草)に生まれる。 |